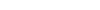✶ 第七幕 キョウトバトル
夜のうちにミカヅキが生け捕りにしたガモンの手下はキョウトタンダイの厳しい取り調べにも口を割らなかったが、シウンが術をかけると、ガシュー一族の作戦について熱に浮かされたようにペラペラと話し始めた。
それによると、もともとは明日中にギュウジを搬送責任者として武器・弾薬が要塞に運び込まれ、明後日にガシュー本人がキョウト入りする手筈だった。しかし、シウンとW-NINJAの急襲を受けてミカヅキに逃げられてしまったため、ガシュー本人も明日、ギュウジとともに、決戦に備えてキョウトに乗り込んでくることになった。
キョウトの秘密要塞は本来、西日本制圧のための拠点であり、今回の作戦はあくまでも武器、弾薬を要塞内に運び込み、備蓄するのが目的だったという。この段階で兼正左近率いるキョウトタンダイ軍と一戦を交えるつもりはなかったのだ。
これを聞いた兼正は複雑な思いを抱いた。シウンの情報提供により、ガシュー一族に不意討ちを喰わずにすんだという安堵とともに、シウンに知らされるまでガシュー一族の動きと狙いを把握できていなかったことへの慚愧の念だ。兼正はこのキョウト決戦が終わり、まだ生き延びていたら長官を辞する決心を固めた。
一方、シウンが我が身の危険も顧みず、ミカヅキ救出のために要塞に乗り込んできたことで、シガツ一族とマリシエイ一派の強い絆を思い知らされたガモンは、ミカヅキを倒さなければ、シウン抹殺という本来のミッションを遂行できないと悟った。
同じころシウンも、コノヘワナキに渡ってアラキリヒルトの秘術を受け、この世の中に平穏をもたらすには、ここキョウトで、ガモンとの闘いに決着を付けるしかないと覚悟を決めていた。
そして、その日の深夜、シウンらが侵入した鴨川の河原の入り口から要塞に、大量の武器、弾薬がベルトコンベアーで次々と運び込まれていった。兼正らはその様子を監視していたが、攻撃は控えていた。ここで攻撃すれば、弾薬が大爆発を起こしキョウトの街の大半が吹き飛ばされかねないからだ。
ミカヅキはそのころ、兼正邸から東方に二キロほど離れた阿弥陀ヶ峰の山頂にいた。豊臣秀吉の墓である豊国廟があり、標高は二〇〇メートル足らずだが、周囲には鬱蒼たる木々が生い繁り、雲が出てきた今宵は光の全くない漆黒の闇に包まれている。
その闇の底で一人、座禅を組み、懐から取り出した小さな蝋燭に火を点す。戦を前にして集中力を極限まで高める禊の儀式、火焔忍術だ。
ミカヅキが印を結び、マリシエイ一派に伝わる独特の言葉で呪文を唱える。その呪文は、一説には、古代ユーラシア大陸北東部に勢力を持っていた騎馬民族が使っていた言葉だとされるが、定かではない。
ミカヅキの呪文が熱を帯びるに連れ、小さな蝋燭の炎が次第に人の背丈にまで燃え上がり、さらには周囲に生い繁る木々よりもはるかに高く燃え上がった。
その火焔に照らされたミカヅキの顔は、日ごろの柔和さが消え、地獄で罪人を裁く閻魔のように恐ろしい形相に変わっている。
儀式は三十分ほど続き、最後に火焔は真っ直ぐに天に昇って行った。ちょうどその時間にキョウトの街から東の空を眺めていた者は、炎に包まれた龍が天に昇って行ったように見えたに違いない。
そして、ついに決戦の朝を迎えた。兼正邸の広大な庭で野営していたキョウトタンダイ戦闘員三百人は午前五時には武装して整列し、戦闘の最終準備に余念がない。四人のW-NINJAはすでにニシキマーケット周辺に散って、続々と結集してくるガシュー一族の戦闘員の動きを監視していた。
ミカヅキは打ち合わせ通り、大文字山の山頂でシウンと合流し、二人そろって朝まだきのキョウト市街全体を俯瞰している。二人は視野の中に、キョウトタワーの先端に立ち、やはり街を見下ろしているNINJAを捉えていた。濃紺の戦闘衣をまとい、大きなマントを折からの強い東風になびかせているガモンだ。ガモンもまた大文字山の山頂にいるシウンとミカヅキを見つめ返していた。
折しも、この年幾つ目かの台風が太平洋を北上し、日本列島を襲おうとしている。その予兆の強風がキョウトの街を吹き抜け、惰眠を貪るこの国の人々に、現代の関ヶ原の戦いとも言うべきキョウトバトル勃発の風雲急を告げている。
今やシウンとミカヅキにとってはガモンを倒すこと、ガモンにとってはシウンとミカヅキを倒すことしか頭になかった。
果たしてシウンはこのキョウトバトルを生き延びて、コノヘワナキへの旅を続けることができるのか? ミカヅキは千年前の血の契りにかけて、ガモンやガシュー一族の魔の手からシウンを守り切ることができるのか?
突然、兼正邸の前を流れる鴨川に稲妻が落ちた。太い水柱が十階建てのビルの高さまで上がり、一瞬、鴨川の水が直径十メートルの広さで干上がり、川底が見えた。キョウトタワーの先端に立つガモンからの宣戦布告だった。
シウンのコノヘワナキへの旅の最大の試練、キョウトバトルの幕が切って落とされたのだ。
続く