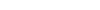✶ 第一幕 旅立ちの儀式
煌々たる満月の今宵。ネオ・トーキョー・シティの西の果て、奥多摩の山中の洞窟では折しも、一人の美しい姫をめぐる神聖な儀式が執り行われていた。
洞窟の天井にポッカリと開いた穴から、青白い月光が射し込み、洞窟の内部に散りばめられた紫色の鉱物の破片を輝かせる。学校の体育館ほどの大きさの洞窟の内部はいたるところ、見事な紫色に染まっている。儀式に集まった人々が「月紫光」と呼ぶ幻想的な自然現象だ。
時は西暦二〇六六年の初夏。ネオ・トーキョー・シティでは、立ち並ぶ超高層ビルの間を縫うように自動車専用レーンが走り、自動運転の「AIビークル」と呼ばれる乗り物が音もなく行き来する。おかげで交通事故はなくなったが、人々が自ら自動車を運転する楽しみを奪われて久しい。肉体労働も大半は作業用ロボットが行い、頭脳労働はAIが代行している。食料は、肉も野菜も魚も工場の中でバイオ技術によって製造されている。
人々の生活の中で、生きるために働く時間は極端に短くなった。残念なことに、科学技術の飛躍的な進歩に反比例して、人間の精神は退化してしまったようだ。ほとんどの国民は趣味や美食、恋愛、ゲームなどにうつつを抜かし、刹那的な快楽に溺れている。
そうした人間の愚かさをあざ笑うかのように、三十年前、巨大な銀河が太陽系に異常接近したため、太陽系の時空にひずみが生じた。そのひずみを通って、過去の様々な時代から様々な身分、職業の者たちが大勢、今の時代にワープしてきたのだ。
当然ながら国中が一時は大混乱に見舞われたが、いずれの時代からやってきたかに関わらず、市井の町人や商人、農民などはすぐに現代社会に溶け込んだ。何しろ、朝廷や幕府のように目に見える形で支配する権力機構はなく、重い年貢を納めるために汗水垂らして働く必要もないのだ。彼らからすれば、現代は天国に等しい。
一方、奈良・平安時代の貴族や、鎌倉から江戸時代にかけての武士といった支配階級の人間たちは、かつての権勢を忘れるとこができず、得意の権謀術数を用い、怠惰な生活に慣れ切った現代人を支配している。自らを都道府県の〝知事大名〟と称して事実上の世襲制を敷き、時として国会議員より大きな権力を握るまでになった。
ワープしてきた人々の中には、各地で暗躍するNINJAの一族も含まれていた。戦闘技術はもちろん、諜報活動や破壊工作、心理作戦などに優れた彼らの能力は、科学が発達した西暦二〇六六年においても大いに威力を発揮することが分かった。そのため、知事大名はそれぞれNINJAの一族を傭兵として囲い込み、自分たちの権力欲を満足させるために、NINJA同士を戦わせているのだ。
ネオ・トーキョー・シティを首都とするジャパンを六年前から統治しているショウアンも、NINJAを使って政権奪取に成功したのだった。自ら〝将軍〟と称し、長きにわたって権力をほしいままにしてきたショウアンだが、今ではショウアンに対する知事大名たちの反発は頂点に達している。
知事大名たちは、隙あらばショウアン政権を転覆し、自らが将軍の座に就こうと企み、NINJAを使って暗闘を繰り広げているのだ。
NINJA同士の闘いは、一般人の目に触れない時空のダークサイドで行われる。それゆえ趣味や快楽に溺れる一般人の目には、この国は平和な世の中に見える。しかし、NINJAにとって現代は、中世の戦国時代に逆戻りしたかのような戦乱の世なのである。
月紫光の夜に聖なる儀式を行っているのは、平安時代から続く由緒正しい一族の一つ、トウキョウ・シティの北西部に位置する奥多摩一帯をテリトリーとするシガツ一族である。
シガツ一族もワープしてきた一族だが、ワープしてきた一般の人々とも、NINJAとも異なる顕著な特徴があった。いつのころからかシガツ一族の棟梁の家に生まれた姫には、乱世に平穏をもたらす特殊な能力が備わるようになったのだ。
そのシガツ一族に二十年前、待望の姫が生まれた。きょう二十歳の誕生日を迎えたシウン姫である。今宵の儀式はシウン姫が成人したことを祝うためである。そして同時に、シウン姫の旅立ちの儀式でもある。
洞窟の一際高い岩場に端然と座っているのが、いずれ一族の第二十七代棟梁となるシウン姫だ。シガツ一族の姫の正装である純白の絹布に色鮮やかな絹糸で精緻な刺繍を施した衣装が、月紫光に照らされ、美しい紫色に染まっている。男の正装である純白の絹の作務衣に身を包み、シウンの傍らに立っているのは、シウンの父親である第二十六代棟梁のペンハーンだ。
数十人の人々が三メートルほど低い平坦な場所に立ち、姫を見上げている。集まった皆は、袖のない色鮮やかな羽織にモンペという一族の正装姿の者もいれば、Tシャツにジーンズやスーツ姿など思い思いの服装の者もいる。
頃合いを見計らってペンハーンがシウンに目配せする。シウンがうなずくのを見て、杖を大きく持ち上げて先端で足元の岩を突く。
カーーーーーーーン。
乾いた音が洞窟の壁に乱反射して響きわたる。その残響音が消えるのを待って、姫がおもむろに立ち上がった。
「おおっ、今夜の姫は一段と美しい!」
二人を見上げる数十人の老若男女が一斉に、感嘆する声を上げた。彼らが正装したシウン姫を見るのは、この夜が初めてだった。
シウンは生まれるとすぐに、山中に広がる彼らの街よりもさらに山奥の秘境に移された。シウンはそこで二十年もの間、一族の棟梁である父親から一子相伝の秘術を受け継ぐため、厳しい修行の日々を送っていたのだ。
とはいえ、修行の傍ら、同年代の者たちと一緒に街を抜け出し、ネオ・トーキョー・シティのロッポンギやニシアザブなどに繰り出す〝現代っ子〟でもあった。にぎやかな盛り場でもシウンの美しさは人目を惹き、芸能人でもないのに数十人もの親衛隊ができるほどだった。もっとも、シウンが修行で得た秘術を使えば、どんなに気の荒い暴漢でもたちどころに戦闘意欲を失い、シウンの前にひざまずくことになる。だから、親衛隊など必要ないのだが、シウンも面白がって彼らを従えているのだ。
だが、今宵のシウンには、そんな浮ついた雰囲気は微塵も感じられない。
姫のやや後方から降り注ぐ月光が漆黒のショートヘアに反射し、頭の上に光輪が浮かんでいるようだ。優しげな眉、愁いを含み濡れたように輝く瞳、高く通った鼻梁、桜の花びらの唇、ふくよかなラインを描く顎がバランスよく配され、見る者を魅了せずにはおかない。
洞窟内の鉱物の破片が紫色に輝いているのは、実はシウンが過酷な修行を行ったときの衝撃でできた副産物だ。そんなシウンの秘めたる力をよく知っているはずの一族の者たちにさえも、今のシウンは幼げで華奢に見える。
「まるで天女のようだ!」
「いや、女神さまだ!」
人々は姫の美しさを賛美する言葉を思い思いに口にし、どよめきはいつまでも収まる気配がなかった。
「皆の者、鎮まれ! 鎮まるんだ!」
棟梁が手に持った杖をブンと一振りすると、強い旋風が皆の顔に吹き付ける。姫の美しさに酔い痴れていた者たちがようやく口をつんだ。
「皆の者、よく聞け。皆も知っている通り、シウンはきょうハタチの誕生日を迎えた。シウンは今宵、コノヘ・アイランドの生き神アラキリヒルトに会うために旅立たなければならない。アラキリヒルトの儀式を受け、我ら一族の姫が天から授かった力を解き放ち、いつの世になっても戦いを続ける愚か者たちの目を覚ます時が来たのだ」
シウンは黙って父親が述べる口上を聞いている。その表情からは、一族の姫に課せられた冒険的な責務を遂行する並々ならぬ決意と同時に、少女から大人の女へと成熟する過渡期の危うさが滲み出ている。
「シウンはこの旅の全ての行程を徒歩または人力で動く船で行かねばならぬ。飛行機やAIビークルはもちろん、旧式のガソリンで走るクルマも使うことはできない。その理由は、皆も知っている通りだ」
この時代、あらゆる個人情報を記録したマイナンバーチップがすべての国民一人一人の身体に埋め込まれている。電車や飛行機などの交通機関や、高速道路や幹線道路による移動は、すべての駅や空港、インターチェンジなどに設置された監視システムに感知され、情報は瞬時に政府が管理するスーパーコンピューターに記録される。さらに、網の目のように張り巡らされた監視カメラシステムともリンクされている。国家はこの「マイナンバー監視システム」により、誰が、いつ、どこで、何をしたか、すべてをリアルタイムで把握できるのだ。むろん、シウンの腕にもチップが埋め込まれている。
シウンが交通機関を使えば、そのシステムをハッキングしている知事大名たちにも筒抜けになる恐れがある。世に戦乱を起こし、その混乱に乗じて天下を取ろうと狙っている知事大名たちがそのとき、シウンの『覚醒』によって平和な世の中が訪れることを嫌い、『覚醒』を阻止しようと動き出すだろう。
「シウンはマイナンバーチップを感知されないよう、キューシュー・エリアのカゴシマまで徒歩で陸路を行き、そこから先は奄美諸島や琉球諸島の島伝いに櫓漕ぎの船で海路を行く。だが、どれだけ注意しても、国家の監視システムから完全に逃れるのは不可能だ。シウンの動きはいずれ、どこかで察知されるのは避けられない。知事大名たちが傭兵であるNINJAを使い、シウンに襲いかかってくることも覚悟しなければならない」
聴衆の間から、シウン姫の前途を心配して悲鳴やため息が沸き起こった。ペンハーンがそれを制して続ける。
「さらに始末が悪いのが、知事大名たちを武力で叩きのめそうとしているショウアン政権による邪魔だてだ」
一番前に陣取っていた若者が「おうっ」という声とともに手を挙げた。
「ダィク、何だ?」
「それだけの苦難と危険があると分かっていながら、なぜ、シウン姫は行かなければならないんだ?」
人々の間から「そうだ」「そうだ」という声が上がる。
「姫もこの村で、私たちと一緒に平穏に暮らせばいいのではありませんか?」
ダィクの隣りにいる同年代の女性が畳みかける。
「今度はフゥか」
ダィクもフゥもシウンの幼馴染みであり、遊び仲間でもある。
「まあ、ワープする前も含めてこの二百年ほどは棟梁の家に娘が生まれてこなかったから、多くの者が知らないのも無理はないか。なぜ、姫が苦難の旅に出かけねばならのか、説明してやろう。わしが先代の棟梁、つまり親父から聞いた話だ。心して聞け」
棟梁ペンハーンが重々しい声で語ったのは、以下のような一族の歴史だった。
シガツ一族は今からおよそ千年の昔、平安時代中期より、比叡山の西麓に生きる一族だった。ところが、室町時代の一四〇〇年代半ばに、京の都では大義名分のない無益な応仁の乱が十年以上も続いた。京に住む民も、戦を続ける領主たちの領民たちも疲弊しきっていた。当時のシガツ一族の棟梁はそんな京に嫌気し、一族を率いてこの奥多摩の秘境に落ちて来た。
「以来、吉宗公の世まで、いずれの領主にも仕えず、争わず、ひたすらに世の安寧を願いながらひっそりと暮らしてきた。それは三十年前にワープした後も同様だ」
一族は徳川八代将軍吉宗の時代から現代にワープしてきたらしい。シウン姫もそうだが、先ほど声を上げた若者らはワープ後に、現代に生まれた者たちだ。
「その間、我らが他の一族や領主に戦を仕掛けたことはむろん、仕掛けられたことも一度たりともなかった。それは、我ら一族の代々の姫に備わる神秘の力ゆえに、ほかの一族から崇められ、畏れられてきたからじゃ」
皆が改めてシウン姫に注目する。この可憐な二十歳の姫に戦乱の世を鎮める神秘の力が本当にあるのだろうか。
「シウンがこの二十年間、修行に励んできたのはひとえに、コノヘ・アイランドに渡り、生き神アラキリヒルトの『覚醒』の儀式を受け、この世の中に平穏をもたらすためだ。姫がアラキリヒルトの儀式を受けず、したがって『覚醒』もしないと分かったら、NINJAたちは、我らを崇めたり畏れたりする理由がなくなり、いつ何時、戦を仕掛けてくるか分からない。いや、それどころか、神秘の力を授かる姫が二度と誕生しないよう、我らシガツ一族を根絶やしにしようとするに違いないのだ」
今度は、シウンよりやや年長と思われる女性が声を上げる。
「姫が旅立たねばならぬ理由は分かりました。そこで棟梁、姫は一人で旅をしなければならないのですか? 護衛の者を付けてはいけないのでしょうか?」
日ごろ、シウンが姉のように慕っているジタンだ。
「おお、ジタンよ、よいことを聞いてくれた。これから話そうと思っていたところだ。シウンの旅に従者を付けることは許されている」
「では、棟梁、私をその従者の一人にしてください」
ジタンがそういうと、先ほど声を上げたダィクとフゥも我先に名乗りを上げる。
「俺も行くぞ」
「私も行きます」
シガツ一族はNINJAではないものの、若者は男も女もそれなりの戦闘訓練を受けている。ペンハーンもシウンの従者には、気心の知れたこの三人を付けようと考えていたところだ。
「お前たち三人が名乗り出てくれて、これほど心強いことはない。ジタン、ダィク、フゥ、シウンを頼んだぞ!」
「オーッ」「オーッ」「オーッ」
一族の全員が右手を突き上げて、雄叫びを上げた。
「シウン、これで旅の支度が整った。我が一族に代々伝わる秘剣をお前に授ける。アラキリヒルトの儀式を受ける際に必要な剣だ。決して奪われてはならんぞ」
それは全長五十センチ、刃渡り三十五センチの女性用の小太刀だった。刃を収める鞘も、握る部分の柄も朴の木で作られており、鍔はない。遠目にはただの一本の黒い棒にしか見えないが、黒漆を塗り重ねた下地に銀彩の蒔絵で一族の守り神である●●が描かれている。刃は後の世にまで名工として名高い伊勢の千子村正の父、美濃の赤坂左兵衛兼村が鍛えた業物だ。
その夜遅く、月が西の山に沈み、辺りが漆黒の闇に包まれると、シウン姫と三人の従者は一族が住む街を音もなく抜け出た。一族の皆は寝静まり、棟梁のペンハーン以外に見送る者のいない寂しい旅立ちだ。
そのとき、街を見下ろす岩壁の上で、気配を消した黒い影がまるで雲のように流れ、山の奥に消えて行ったが、それに気づいた者はいなかった。シウンらの旅立ちの様子を見ていた者が、もう一人いたのだ。
街を出たシウン一行は青梅街道を西に進み、奥多摩湖の上流にかかる深山橋を渡って国道一三九号線を進み、間もなく山梨県に入った。小菅村池之尻から山梨県道五〇八号線をさらに西に向かい、県道が尽きるところから登山道に分け入る。
月明かりもない山道を、かすかな星の光だけを頼りに速足で登って行く。修行を積んだ者でなければ、一歩たりとも前に進めないであろう。シウンも三人の従者に後れを取ることなく、なめらかに歩みを進めている。
一行は夜明け前に、登山道の頂上にある大菩薩峠にたどり着いた。日の出の直前のコバルトブルーの光の中で、海抜千八百九十七メートルの大菩薩峠から見下ろす甲府盆地は、雲海の底に沈んでいる。その遥か南では、雲海を突き抜けて富士山が堂々たる姿を見せている。まるで絶海に浮かぶ孤島のようだ。
シウンは修行の一環として大菩薩峠に何度か登ったことがあったが、薄明りの中で見る雄大な風景に、改めて目を見張る。そして、感動を覚えると同時に、これからの旅路の長さを思い知らされたのだった。
ジタンが焚火を起こして湯を沸かし、四人は簡単な食事を摂る。科学技術の粋を集めて作られた栄養バランスのいい宇宙食だ。
束の間の食事が終わると、焚火の形跡が残らなくなるまで徹底的に始末し、迷彩柄のマントにくるまってひと時の眠りに就く。
一時間ほど経ってジタンが目を覚ましたとき、太陽はすでに東の関東山地の山の端を離れていた。ジタンがダィクとフゥに囁く。
「監視されているな」
「ああ、四方に一人ずつ、合計四人だ」
ダィクが答えると、地面に耳を付けていたフゥが続く。
「今のところ、襲撃してくる気はなさそうだ」
シガツ一族のシウン姫が二十歳になり、コノヘワナキに向けて旅立ったことは、一族の集落を見下ろす崖の上から雲のように消えた斥候の情報として、一夜のうちにある流派のNINJAに伝わっていたのだ。やがて、各地のNINJAの流派に伝わるのは避けられない。
三人の中でいつしかリーダーとなっている最年長のジタンが、身支度を整えているシウンに話しかける。
「姫、後をつけられています。気づいていないふりをしてください」
「やはり、そうか。仕掛けてくる気配は?」
「今のところは、ありません。そろそろ出発しましょう」
シウンはすっくと立ち上がり、リュクを背負う。その出で立ちは山歩きを楽しむ普通の若い女性の服装と変わらないが、神秘性を湛えた美貌を隠すことはできない。護衛を兼ねる三人の従者も、朝日を浴びたシウンの美しさに心を奪われ、思わず見とれてしまう。
ジタンらは気づいていないが、実はもう一人の追跡者がいた。第五の追っ手は一キロほど離れた岩陰に潜み、シウン一行の様子をつぶさに観察していたのだ。
シウン一行は、急峻な斜面を甲府盆地に向かって滑るように駆け下りて行く。盆地の南端を流れる笛吹川沿いに進み、釜無川と合流して名前が富士川と変わる地点に差しかかるころ、一般の人々の日常活動が始まった。
シウン一行は思い思いにハイキング用のウエアを着て、富士川の西岸を走る国道五二号線、通称身延道を南下する。普通のハイカーと違うのは、四人がオリンピック級のマラソンランナーにも負けない速さで進んでいることだ。
四人の追跡者はそのNINJA流派に特有の戦闘服に身を包み、一般人に見つからないように、ある者は山中の獣道を、ある者はゴツゴツとした石が転がる河原をといった具合に、およそ五百メートルの距離を置いてシウン一行の前後左右を包囲して移動している。
身延道は富士川が下流域に差し掛かる辺りで富士川を離れ、南西に転じる。その後、山梨県と静岡県の県境の田代峠を源流とする興津川沿いを下って行き、駿河湾に突き当たる。
一行が駿河湾に到達したとき、時刻はまだ正午前。大菩薩峠からここまで百数十キロの道程をおよそ五時間で踏破したことになる。しかし、四人とも呼吸も乱れず、汗もかいていない。
「姫、ここらで少し休みましょう」
ジタンがシウンに呼びかけ、一行は興津川の河口から海に突き出た砂洲に下りる。周囲の気配を伺うと、四人の追っ手は相変わらず五百メートルの距離を保って遠巻きにしている。やはり、すぐに襲いかかってくる様子はない。
四人は砂洲に車座に腰を下し、朝と同じ宇宙食を食べ始めた。
「姫、この分なら今日中にコライミサキまで行けそうですね」
ジタンがそう話しかけた直後だった。
快晴の空が一転、真黒な雲に覆われたかと思うと、耳をつんざかんばかりの雷鳴とともに、シウンのすぐ後方の海面から大きな水柱が上がった。稲妻が波打ち際に近い海面を撃ったのだ。三十メートルの高さに達した水柱は、集中豪雨のようにシウンらの上に降り注ぐ。シウンらが気づいていなかった第五の追っ手が忍術を使って落とした稲妻だった。
この瞬間に、これから果てしなく続くことになる戦いの幕が切って落とされたのだった。