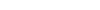✶ 第二幕 CYBORG NINJA ガモン誕生
ネオ・トーキョー・シティのシンジュクにそびえる巨大な墓石に似たビルの地下深く、三メートルおきに青白いライトが灯る廊下がどこまでも続いている。カントウ・エリアで絶大な権力を持ち、次期ショウグンの座を狙うガシュー一族の牙城トチョウビルの地下だ。
地上階にはネオ・トーキョー・シティの地方自治を担うヤクショがあり、四万人近い職員が働いている。その地下には、ガシュー一族の秘密要塞がある。ガシュー本家から分かれた分家の棟梁たちや、ハッキングや盗撮盗聴、誘拐などの〝裏仕事〟をする犯罪の専門家、そして忠実な傭兵であるNINJAたち以外に、その存在を知る者はいない。
地上階には一応は議会もあるが、言ってみれば、そこの議員たちは〝お飾り〟だ。彼ら自身もそれとは知らず、有権者という名前の領民向けに〝政治ごっこ〟のパフォーマンスを演じているに過ぎない。
一族の、そしてネオ・トーキョー・シティの命運を左右するような重要案件は、すべて地下の秘密要塞の中にあるオペレーションルームで決められる。テニスコートほどの大きさの部屋の中央には、二十人がゆうに着席できる楕円形のテーブルが置かれている。正面の壁には特大の3D有機液晶パネルが据え付けられ、他の三面の壁には大小様々な大きさのパネルが並ぶ。トーキョーエリアのあらゆる場所に網の目のように設置された監視カメラの映像をリアルタイムで映し出したり、街頭やコーヒーショップなどでのヒソヒソ話を盗聴したりすることも可能だ。
これは他のエリアの知事大名たちには内緒だが、ガシュー一族は全国の空港や鉄道駅、バスターミナル、港などに設置された監視カメラのデータを常時ハッキングしており、それらの映像もリアルタイムで映し出すこともできる。シウンが公共交通機関を避けなければならない理由の一つがここにある。
その薄暗い廊下を二人の男がストレッチャーを押して奥へ、奥へと急いでいる。ストレッチャーに仰向け横たわっているのは、屈強な若者だ。顔色はよく、気力も充実しており、どこも悪いところなどなさそうに見える。ストレッチャーを押す二人の方が余程不健康そうだ。
「ガモン様、もうすぐ到着します」
「手術屋の腕は確かですから、ご心配は無用です」
ガモンと呼ばれた若者は、不敵な笑みを浮かべて答える。
「心配などするものか。どんなサイボーグNINJAに改造してくれるのか、楽しみだぜ」
ストレッチャーはさらに廊下を進み、最奥部の観音開きの扉の前で止まった。扉が音もなく開くと、その室内にはまばゆいばかりの光が溢れていた。最新鋭の機器を集めた手術室だ。
その中心の天井から吊るされた巨大な無影灯の下で、真っ黒い手術着を着た男が立っている。一族の者から〝手術屋〟と呼ばれる医師だが、見るからに怪しげで、全身から邪悪なオーラを発している。
その手術屋が、ガモンに対して媚びへつらう態度で接する。
「ガモン様、ご気分はいかがですか?」
「そんなことはどうでもいい。さっさと手術に取りかかってくれ」
「ご希望の通り、麻酔は使いません。代わりに鍼を使って、脳に痛みを伝える神経をブロックします」
ガモンは手術屋らを完全に信用しているわけではなかった。ガモンは麻酔で意識が飛んでしまい、手術中に寝首をかかれることを嫌ったのだ。
「ですから、意識はハッキリしていますが、痛みを感じることはありません。よろしいでしょうか?」
ガモンがうなずくと、手術が始まった。先ほどストレッチャーを押していた二人の男たちも黒い手術着に着替えている。どうやら助手を務めるらしい。
まずは、神経の情報伝達機能を遮断するために、ガモンの全身に百本以上の鍼が打たれた。手術屋は見事な手さばきで、大小の鍼を次々と経絡のツボに打って行く。それでも、打ち終えるまでに一時間はかかった。
続いて手術屋は、ガモンの左の目にメスを入れ、眼球をえぐり出す。空洞となった眼窩に眼球と同じ形、同じ大きさの球体が埋め込まれる。超高性能カメラ付の眼球型コンピューターだ。ガシューの秘密要塞の地下深くに設置されたスーパーコンピューターと常時接続されており、カメラが捉えた画像や、視野の中にいる人間のマイナンバーチップの情報が瞬時にやり取りされる。それにより、その者が何者で、敵か味方か、NINJAだとすればどんな技や武器を使うのかといった〝個人情報〟が瞬時にガモンの脳に伝達される。ガモンの前に立つものは誰も、たちまちのうちに丸裸にされるのだ。
さらに、肩、肘、股間、膝の関節がすべて人工関節に交換された。強力なパワーを持つ小型モーターが内蔵されており、投擲力や跳躍力が飛躍的に増強される。
十時間以上にわたる外科手術が終わったとき、ガモンは身体中を切り刻まれ、全身血まみれだった。完璧に止血はされているが、傷口を縫った跡が痛々しい。並みの人間、いや鍛錬を重ね修行を積んだNINJAでも、意識を保ったままこれだけの大手術を受けるのは不可能だろう。ガモンが並外れた精神力の持ち主であることが分かる。
外科手術が終わると、手術屋は直径二十センチほどの水晶のように透明な珠を持ち出してきた。その珠を両手で捧げ持ち、ガモンの身体から十センチほどのところを、頭のてっぺんから足先まで、ゆっくりと往復させる。
十往復させるころには、ガモンの身体にべったりと張り付いていた血がきれいに消えた。さらに十往復させると、手術の傷跡までが消えてしまった。
外科手術で要所の関節をサイボーグ化したガモンだが、骨や筋肉が以前のままでは、かえって身体を壊してしまいかねない。骨や筋肉を強化する必要があるが、それは外科手術では無理だ。また、人工眼球や人工関節の電子回路とガモンの神経の接合も人間の手はもちろん、外科手術のために開発されたロボットフィンガーでもできない。
手術屋が傷跡が消えた後もなお、透明な珠をガモンの身体の上で往復させ続けているのはそのためだ。
注意深く観察する者がいれば、ガモンの身長が徐々に伸びていき、身体中の筋肉が盛り上がり太くなっているのに気づいたはずだ。左の目蓋の裏で、人工眼球も動き出した。
この小さな珠から発せられる何かが、ガモンの身体を内側から回復させ、さらに増強しているのだ。
この珠はガシュー一族に代々伝わる家宝の一つ、冥王星の彼方から地球に飛んできたウラヌス隕石だ。不思議な霊力を帯びており、千数百年の間、ガシュー一族を滅亡の危機から何度も救ってきた。ガシュー一族が持っている宝物は山ほどあるが、この隕石は数ある宝物の中でも別格だった。
ウラヌス隕石は通常、秘密要塞の中にある金庫に収められ、その金庫は十人のNINJAたちによって二十四時間体制で警備されている。今日は特別に、二倍の二十人がこの手術室を取り巻くように守りを固めており、手術が終わるまで蟻一匹たりとも、忍び込むこともはい出ることもできない。
それほど大切な隕石の霊力をガモンに授けようというのだから、ガシュー一族がいかにガモンに目をかけてやっているか分かろうというものだ。
手術屋がようやく珠を頑丈な超合金ケースに収め、ガモンに声をかける。
「ガモン様、まず腕を動かしてみてください」
ガモンが両腕を垂直になるまで持ち上げ、肘を曲げた。
「今度は、脚を動かしてみてください」
ガモンが脚を持ち上げ、膝を曲げる。すべての動きが極めてスムーズだった。ウラヌス隕石の霊力で、ガモンの神経が人工関節の回路に完璧につながり、ガモンの意思通りに動く。
「うむ、手術屋、上出来だ」
「ありがとうございます、ガモン様。一つご注意いただきたいのが、すべての筋肉が以前の十倍以上に強化されております。お慣れになられるまでは、意識して力を加減していただきますよう」
「分かった。注意しよう」
「では、立ち上がって、これを身に着けてみてください」
ガモンが手術台から降り立つと、身の丈は二メートル近くに達していた。下着、半襦袢、袴、手甲などすべて群青色の忍者衣装を順番に着ていき、最後にやはり群青色の鎧を身に着ける。それだけで見る者を圧倒するオーラが発せられる。
ガモンは戯れに左手で手術屋の胸倉をつかむと、そのまま軽々と天井近くまで持ち上げる。
「ガ、ガモン様、く、苦しゅうございます」
ガモンは新たに身につけた力に満足し、手術屋をゆっくりと床に下ろしてやる。
「ご満足いただけましたでしょうか?」
手術の一部始終は、無影灯に設置されたカメラを通じて〝実況中継〟され、オペレーションルームの大型モニターに映し出されていた。
だだっ広いその部屋でただ一人、モニターを食い入るように見つめていたのは、ガシュー一族の重鎮のギュウジだ。自らも武闘派のNINJAである。
ガモンの身体のいたるところが切り刻まれ、血まみれの筋肉や骨が露出しても表情一つ変えなかったギュウジだったが、手術を終えたガモンが手術屋を片手で軽々と持ち上げるのを見て、思わず深い満足の笑みを浮かべた。
「間に合ったな。これで、シウンの命運は尽きたも同然だ」
ギュウジのもとには昨夜、二十歳の誕生日を迎えたシガツ一族の姫シウンが、生き神アラキリヒルトが住むコノへワナキ・アイランドに向けて旅立ったという知らせが届いていたのだ。
まもなく、オペレーションルームのドアが開いて、ガモンが入ってきた。棟梁の椅子に座るギュウジの前に進み出て、両足を肩幅に開き、胸の前で右手の拳を左手のひらで包む。DENNOの最敬礼のポーズだ。
「おお、ガモン。手術はうまくいったようだな」
「はっ」
ギュウジが手で制すると、ガモンはようやく最敬礼のポーズを解いた。
「体調はどうだ?」
「はっ。ウラヌス隕石の霊力のおかげで、何もかも快適です」
「手術が終わったばかりですまんが、早速、一つ仕事を頼む」
「心得ております。シガツ一族のシウンのことですね」
「さすがはガモンだ。話が早い」
ガモンが時間を意識すると、眼球型コンピューターがガモンの脳に正確な時間を伝達する。
「今は午前三時過ぎですから、夜明け前には大菩薩峠あたりで追いつけます」
「そんなことまで分かるのか?」
「シウン出立の第一報以来、四人の部下に後を追わせております」
「抜かりがないな。では、頼んだぞ」
「はっ!」
次の瞬間、ガモンの姿はオペレーションルームから消えていた。
トチョウビルの地下駐車場にガモンが姿を現すと、停まっていた黒塗りの大型AIビークルの運転席から、黒装束の男が降りてきた。
「ガモン様、甲府までお送りいたします。どうぞ」
「いや、それには及ばぬ。ウォーミングアップがてら、この脚で走って行こう」
ガモンはそう言うと、地上に出て甲州街道を西に走り始め、西参道口の交差点を超えたところで、上を走る首都高速道路四号線に軽々と飛び上がった。高さ十メートル以上の跳躍だ。
首都高速は自動運転のAIビークルが等間隔の車間距離を保ち、時速80キロのスピードで流れている。突然、その高速道路に人間が現れ、男女のカップルが乗る一台のAIビークルの脇を並走し始めたのだ。ガモンはウインドウ越しに驚愕の表情を見せるカップルに手を振ると、さらにスピードを上げ、前を行くAIビークルを次々と追い抜いて行った。
ちょうどそのころ、トチョウビルの屋上から夜空に向かって、一人乗りのドローンが音もなく飛び立った。搭載されたAIが四つのプロペラの回転度速度を変えたり、ローターの軸を微妙に傾けたりして、進行方向や高度、速度を調節する。コックピットに乗っているのは、濃紺のNINJA装束に着替えたギュウジだ。
「ガモンがシウンをどう始末するか、高見の見物と洒落込むか」
ナビ画面では、地図の中央高速の上を赤いポイントが点滅しながら移動している。ガモンに埋め込まれた人工関節の一つから発せられる電波を捉え、ガモンの位置情報が表示されているのだ。ギュウジが乗ったドローンは、ガモンの後方三〇〇メートル、高度二〇〇メートルの上空から、疾走するガモンを追尾する。ガモンのサイボーグ化手術の出来映えを確認すると同時に、ガモンが命令通りにシウンを抹殺するかどうか監視するためだ。
ガモンはすぐにドローンに尾行されていること、乗っているのがギュウジだと気づいたが、別に驚きもしなかった。猜疑心の強いギュウジの性格からして、自分が監視されることは予想していたからだ。
ただ、少し意外だったのは、ギュウジ自身が尾行してきたことだ。今回のシウン抹殺の任務が、ガシュー一族にとってそれだけ重要だということを示している。
ガモンは高井戸ICで中央自動車道と名前が変わった高速道路を、府中、八王子、上野原と快調に走り続ける。山梨県大月市を過ぎ、全長四七一七メートルの笹子トンネルを抜けた甲州市甲斐大和で高速道路から飛び下りた。トチョウビルを出てからここまでちょうど一時間。距離はおよそ百キロだから、時速一〇〇キロの速さで走り続けたことになる。ガモンは額にうっすらと汗を浮かべているだけで、疲れの色は全く見えない。
「ふふふふふっ、ウォーミングアップしたほどの疲れも感じない。アンドロイド手術とウラヌス隕石の霊力がこれほど凄いとは」
ガモンは改めて満足そうな笑みを浮かべると、ガモンは休む暇も惜しんで、また走り出した。甲斐大和から日川沿いを走る県道二一八号線を北上すれば、大菩薩峠までは二十キロ余りだ。
一方、ギュウジが乗ったドローンに搭載したAIは、ガモンを追って笹子トンネルに進入するのは避け、標高一三五七メートルの笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま)を迂回するルートを選択した。飛行可能高度は約一〇〇〇メートルほどだ。
そのため、ギュウジが乗ったドローンが笹子雁ヶ腹摺山の麓を流れる笹子川の上空を飛び、笹子トンネルの甲州市側の出口に着いたときには、ガモンの姿はすでになかった。だが、ドローンのナビ画面の赤い点滅は中央高速を逸れ、北へ向かっていた。
「ガモンは予定通り、大菩薩峠を目指しているようだ」
だが、このドローンで標高一八九七メートルの大菩薩峠まで追っていくのは無理だ。しかも、様々な最新鋭センサーを搭載しているとはいえ、漆黒の闇に包まれた山中を飛行するのは危険だ。
ドローンに搭載されているAIは、シウン一行とガモンたちを待ち受ける場所として、大菩薩峠から甲府盆地に下ったところにある石和温泉郷を推奨してきた。シウン一行が重川沿いに下って来るとすれば、笛吹川と合流する石和温泉郷を抜けて行くに違いない。確かに、待ち伏せに適した場所と言える。むろん、ガモンが大菩薩峠でシウンらを始末していなければの話だが……。
「まあ、しばし足湯に浸かってのんびりとするか。果報は寝て待てと言うしな。ふぁはっはっはっはっはっ」
ドローンはしばらくして、JR中央本線石和温泉駅の駅前広場に着陸した。ここに一般に開放されいる足湯がある。夜明け前のため、ギュウジのほかに誰もいない。
ギュウジが降りると、ドローンは無人で上昇し、上空で待機する。ギュウジがくつろいでいる間も、暗視機能付きの高性能カメラでシウンらの接近を監視しているのだ。
一方、急な上り坂が続く曲がりくねった山道を一気に駆け登ったガモンはそのころ、大菩薩峠から一キロほど離れた尾根の岩場に身を潜めていた。そこからは大菩薩峠が見晴らせるはずだが、夜明けにはまだ間があり、辺りは漆黒の闇に包まれている。
しばらくするとガモンの狙い通り、大菩薩峠が夜明け前のコバルトブルーの光を受けてその姿を現し、四人の登山者が峠にたどり着くのが見えた。その身のこなし方を見れば、一般の登山客でないのは明らかだ。第一、真夜中に急峻で危険な登山道を登ってくる一般人などいない。
その四人を遠巻きにする四人の追っ手も確認できた。追っ手たちには、自分たちの気配を完全には消さず、尾行していることをわざと悟らせるように命じてある。
ガモンがもっと細部まで見たいと念じると、左目の眼球型コンピューターに内蔵された高性能カメラがズームインしていく。脳裏にその映像が像を結ぶ。
女三人と男一人だ。その中の一人、飛び切り美しい娘がいる。一般の登山客と変わらない服装ながら、一キロの距離を隔てても感じられる強力なオーラは、シウン姫のものに違いない。
シウン一行は湯を沸かして食事をした後、仮眠を取った。まだ追っ手の存在に気づいていないらしく、驚くほど無警戒な眠りだ。
ガモンは四人をこの場で葬ってしまおうかと思ったが、二十歳になったばかりの美しい娘をすぐに始末するのは惜しいと考え直した。もう少し生かしておき、猫が捕まえたネズミをいたぶるように、シウンを追い詰めて楽しみたいと思ったのだ。その油断が後に、自らを窮地に陥れることになるとも知らずに……。
一時間ほどで目を覚ましたシウンたちは、ようやく追っ手に気づいたようだ。そそくさと仕度し、急峻な斜面を甲府盆地に向かって滑るように駆け下りて行く。ガモンが放った追っ手たちも遠巻きの包囲網を維持したまま、滑り降りて行く。
追われる者と追う者は一定の距離を保ちながら、重川沿いに甲府盆地に入って来た。ドローンはシウン一行を発見すると、すぐさまギュウジを乗せて飛び立つ。シウン一行の四方をガモン配下のNINJA四人が遠巻きに追跡し、さらにその後方にガモンの姿があった。
ドローンのAIの読み通り、シウンらは石和温泉郷の東側で重川に合流した笛吹川に沿って進み、さらに笛吹川が釜無川と合流して名前が変わった富士川沿いに南下する進路を取る。
ガモンはそれを見届けると、彼らから離れ、南アルプス山脈を迂回するため中央自動車道を北上する。そのガモンの行動はギュウジの指示によるもので、キョートに向かったのだ。ギュウジはシウン一行の後を付けて行く。
ガモンは中央道からナゴヤを超えて名神高速道路と名前が変わった高速道路をひた走り、一般の人々の通勤通学のラッシュのころ、キョートに到着した。
何十年か前、年号が平成から令和に変わるころ、政府はしきりと「働き方改革」などと叫んでいたが、変わったのは人々が以前よりも怠け者になっただけで、皆と同じ時間に出勤し、皆と同じようにダラダラと残業するという習性は変わらなかった。実質的な仕事はAIがしてくれるため、人間が仕事を怠けて遊興に耽るようになった。その分、逆に人間の堕落が進んでしまったと言える。
キョートでは、DENNOの築城専門集団が、密かに要塞を築いていた。ガシュー一族の棟梁がショウグンとなった暁には、この要塞が西日本の知事大名たちに睨みを利かせる拠点となる。
要塞は歴史的な街並みが残されているナカギョークのニシキマーケットの近くにある。外観は何の変哲もない町家だが、地下深くに巨大な空間が造られている。これに様々なIT機器や武器が運び込まれている。言わば、トチョウビル地下の秘密要塞のミニチュア版だ。ガモンは彼らの働きぶりに満足すると、すぐに東に取って返す。
シウンたちを追う部下と連絡を取り、正午前、興津川の河口で休憩するシウン一行に追い付くことができた。一キロほど離れた貨物の積み出し港の岸壁に停まっているドローンを確認し、ガモンはニヤリと笑った。これからシウンたちの仕掛ける攻撃は、ギュウジがドローンに乗って空中にいては都合が悪いのだ。
ガモンは河口から一〇〇メートルほど離れた十階建てホテルの屋上に立ち、シウン一行を改めて観察する。シウンたちはガモンが放った四人の追っ手を警戒してはいるものの、相変わらずガモンには気づいていない。そのことが手に取るように分かった。ガモンの心に、傲慢にも失望の念が生まれていた。
「素人同然のこの連中にこれ以上付き合うのは時間の無駄だ。シウン、お前には気の毒だが、ここで始末させてもらうぞ」
ガモンは両足を踏ん張り、両腕を胸の前で交差させて印を結ぶ。
「キエエエエエエエエエエエエエエエッ!」
鋭い気合とともに十本の指を天に向けて開くと、指の先から発せられた波動がまるで昇龍のように力強く天に伸びていく。すると、それまで快晴だった空がたちまちの内にかき曇り、激しい雷鳴とともに太い稲妻が河口付近の海面に突き刺さった。
その雷鳴は一キロ離れた岸壁にいたギュウジの耳にも聞こえた。同時に、海面から巨大な水柱が立ち上がり、三〇メートルの高さから海水が滝のようにシウンたちに降り注ぐのが見えた。