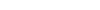✶ 第三幕 NINJYAミカヅキ参上!
興津川河口の砂洲で昼食のため休憩していたシウン一行の至近距離で、突然の稲妻が海面を撃った。太い水柱が十階建てのビルの高さにまで立ち上がり、次にはシウンたちの上に滝のように降り注ぐ。これだけで、シウンを除く三人はパニックに陥っている。水柱が稲妻によるものだと見極めたシウンは、咄嗟に身をひるがえすと、今しがた稲妻が落ちたばかりの海面に立つ。稲妻は同じ場所に続けて落ちないと知った上での冷静な行動だ。
「シウンよ、なかなかやるじゃないか。ますは三人を片付けて、じっくりと遊んでやるぞ」
ガモンは高みから気合を発し、三人が右往左往している砂洲に稲妻を落とす。三人はウラヌス波動を含んだ電撃に跳ね飛ばされ、砂洲に倒れて動かない。
「姿を見せなさいっ! 卑怯者っ」
三人がいとも簡単に打ち倒されたにも関わらず、その声にはシガツ一族の姫としての威厳が備わり、動揺の欠片すら見せない。
ガモンがホテルの屋上から砂洲に飛び降りてきた。まるで鷹が舞い降りるように静かに滑空し、砂粒一つ蹴散らすことなく、砂洲に立つ。シウンとの距離は十メートルほどだ。
「姿も見せず、いきなり攻撃を仕掛けてくるとは、卑怯ではないですか?」
「だから今、こうしてお前の前に立っている」
「名は、何と言う?」
「DENNOのガモンだ」
「私をシガツ一族のシウンと知っての狼藉ですか?」
ガモンがゆっくりとうなずくと、シウンは砂洲に倒れてピクリとも動かないジタンら三人を見ながら、言葉を続ける。
「私の仲間をひどい目に遭わせて、一体、何が目的です?」
「心配するな。三人は半日もすれば意識が戻る。あんな雑魚はどうでもいい。お前がコノへワナキに行くのを阻止するのが、俺の仕事だ」
「では、狙いは私の命ですか?」
シウンは相変わらず落ち着き払っている。ガモンには、シウンの落ち着きが不思議だった。自分の命が狙われているのに、どうしてこれほど落ち着いていられるのか? そして、自分を恐れていないことが気に入らなかった。
シウンは二十歳の誕生日を迎えるまで、一族の皆と離れて暮らし、一族の棟梁である父親ペンハーンの元で厳しい修行を積んできた。それは敵を倒すための修行ではなく、心を無にして、敵の攻撃の威力を相殺する法術を身に着ける修行だ。「無」を攻撃することはできない。
だからこそ、シウンは落ち着き払っていられるのだった。
だが、頭に血が上っているガモンには、そんなシウンの力を見抜くことができない。
「その強がりも、ここまでだ」
ガモンがそう言ってシウンに向かって一歩踏み出そうとしたその時だった。一陣の風と共に、頭巾、上衣、手甲、袴まで黒ずくめの装束に色鮮やかな脚絆をまとったNINJYAが現れ、シウンとガモンの間に割って入った。
ガモンにはそのNINJYAの装束に見覚えがあり、このNINJYAとは以前にも戦ったことを思い出していた。
「お前は、マリシエイ一派のミカヅキだな」
「いかにも、俺はミカヅキだ。ガモンとやら、お前はなぜ、俺の名前を知っている?」
ガモンもミカズキも、戦いの装束を身に着けている。戦いの衣装を着た忍者同士が対峙すれば、お互いに命がけの戦いをするのがNINJYAの定めだ。だが、シウンをかばうようにやや半身で立っているミカズキの構えには、身体のどこにも力みが感じられない。シウンと同様に、心も身体も自然体なのだ。
おまけに、ガモンがミカヅキと過去に戦ったことがあるのを覚えていたにも関わらず、ミカヅキはガモンのことを覚えていない様子だ。
そのことにプライドを痛く傷つけられたガモンは逆上し、得意の印を結んで二人の頭上に稲妻を落とす。二人とも浅瀬に立っているので、たとえ稲妻の直撃を逃れても、ウラヌス波動と感電を避けることはできないはずだ。
だが、稲妻が海面を撃ったとき、二人の姿はすでにそこにはなかった。上空の黒雲から稲津が放たれる直前、ミカヅキは流れるような動作でシウンの身体を抱きかかえ、河口の堤防の上に移動したのだ。そのままシウンを堤防の裏に隠す。
ミカヅキが再び堤防の上に立ったとき、両手に三日月形の剣を持っていた。隕石が月に衝突した際に地球に落下してきた月の鉱石で作った月鉱綫という武器だ。
「ガモンよ、お前の〝稲妻落とし〟は一度ならず二度までも見せてもらった。もはや俺には通用しないぞ」
一度見せてしまった術を同じ相手に二度と使えない。相手のNINJYAが即座に防御策を講じるからだ。それは忍術の基本中の基本なのに、ガモンはそれを忘れるほど頭に血が上っていたのだ。
「くそっ! 俺としたことが。これはどうだっ!」
今度は、右手の五本の指をミカヅキの胸に突き刺すように手を伸ばすと、指先からウラヌス波動が真っすぐにミカヅキに向かって放たれる。すると、ミカヅキは胸の前で二本の月鉱綫を交差させ、ウラヌス波動をガモンに向けて跳ね返す。ガモンは身を翻してかわしたが、危うく自分が放ったウラヌス波動にやられるところだった。
ガモンが態勢を崩している間に、ミカヅキは砂洲に飛び降りてきた。
「その怪しい波動は、すでに見切ったと言ったはずだ。悪いが、今度はこちらから攻めさせてもらうぞ」
ミカヅキは右足を前に出して腰を落とすと、両手に持っていた月鉱綫を背中の鞘に収める。そして、右手の人差し指と中指を拳銃の銃身のように伸ばし、ガモンの足元に向けて気合を放つ。すると、足元を取り巻く砂がガモンの身体を囲むように激しく吹き上がる。足元に蟻地獄のような砂の穴が広がり、ガモンの身体が沈み込んでいく。不意を突かれて態勢を崩したガモンに、ミカヅキは目にも止まらぬ速さで月鉱綫を鞘から抜き、打ち込んでくる。
「何の、これしき!」
ガモンが砂洲から飛びのいて浅瀬に立つと、今度は無数の海洋生物がガモンの身体に食らいついてくる。大小の魚はもちろん、エビやカニ、クラゲまでがガモンの身体を覆いつくす。ガモンが手で払っても払っても、次から次へと新たな海洋生物が食らいつき、貼りついてくる。その間も、ミカヅキは月鉱綫を打ち込んでくる。
ガモンは防戦一方となり、ウラヌス隕石の霊力を振り絞り、身体に貼りついた海洋生物を一気に払い落とす。だが、ようやく海洋生物を払い落としたと思ったら、今度はカモメやトンビ、果てはスズメまでもが、嘴から尻尾まで一直線に伸ばし、矢のようなスピードでガモンに向かって飛んでくる。ガモンがウラヌス隕石の霊力でバリアを作ると、鳥たちはバリアに跳ね返され、砂浜や海に墜落する。
ガモンはこのとき初めて、一度に使えるウラヌス隕石の霊力に限りがあることを知った。バリアが弱まり、ガモンはバリアを突き抜けてきた鳥を手刀で叩き落さざるを得なくなった。
「ガモンよ、どうやらお前の怪しげな霊力も尽きたようだな」
すべてを見抜かれていた。おそらくミカヅキは、シウン一行が奥多摩を出たときから密かに警護していたに違いない。そして、一行に四人の追っ手がついていたことも、大菩薩峠でガモンが追っ手に合流したことも知っていたはずだ。ガモンが追っ手と別れ、一旦は西に向かい、ここ興津川の河口で舞い戻ってきたこともすべて知られていたはずだ。ガモンは自分たちが見張られていることに気づかず、挙句には調子に乗って得意技の〝稲妻落とし〟を二度も披露してしまった。
シウンらに不意打ちを食らわしたつもりが、自らの慢心ゆえに、逆に自分が不意打ちを喰らってしまったのだ。アンドロイドNINJYAとしても力量も見抜かれているに違いない。ガモンは自分の愚かさ、傲慢さからきた油断を、いくら悔やんでも悔やみきれなかった。
ガモンは最後に残っていた霊力で指先から波動を起こし、ミカヅキの足元の砂に向けて放った。男が飛び上がって波動をかわす間に、ガモンは最初にいたホテルの屋上に飛び上がり、そのまま姿をくらました。
ガモンとその部下たちの気配が遠くに離れたのを確認すると、ミカヅキは堤防の陰に隠れているシウンのもとにやってきて、静かに声をかける。
「姫、これで、あの男もしばらくは襲って来ないでしょう」
シウンはなぜか、ミカヅキの顔を見るのが恥ずかしく、視線を足元に落とす。
「ミカヅキ様、あなたがそう言われるなら、間違いないでしょう。危ないところ、本当にありがとうございました。何とお礼申し上げたらいいか……」
「いえ、礼などご無用に願います。では、私はこれにて」
シウンが慌てて顔を上げたとき、ミカヅキの姿はすでに一陣の風と共に消えていた。
その時、シウンはふと、父親のペンハーンから聞かされたNINJYAマリシエイ一派のことを思い出した。遠い昔、シガツ一族の棟梁とマリシエイ一派の棟梁が『血の契り』を交わし、シガツ一族の姫が窮地に陥った際には、マリシエイ最強のNINJYAが必ずや助けに現れるというのだ。
それはおよそ千年前の平安時代中期、一族が南九州の父祖伝来の地を追われ、京都の比叡山の麓にたどり着くまでの流浪の時代のことだった。
シガツ一族は古墳時代より南九州一帯で、隼人と呼ばれた人々と共存していた。ところが、奈良時代に入ると、南九州にも朝廷の権力が及ぶようになり、薩摩国と大隅国に分割された。さらに平安時代になると、荘園の開墾が進み、中央政府に任命され赴任した国司が強大な権力を持って治める支配体制が確立された。
シガツ一族は名望ある豪族でありながら、中央政府の官職に就かず、権力とは一線を画してきた。しかし、年貢や税の徴収など荘園管理の手先としてシガツ一族を使おうと考えた国司は、シガツ一族の棟梁に対し、下級の官職に就くよう執拗に求めていた。棟梁は長らくその誘いを体よく断ってきたが、 他者を支配することも、他者から支配されることもよしとしないシガツ一族にとって、南九州は次第に住みづらい地となっていった。
シガツ一族の不服従に業を煮やした国司がついに一族の弾圧を図るに至り、当時の棟梁は父祖伝来の地、南九州を離れる苦渋の決断を下したのだった。
こうして新たな安住の地を求めて、一族数百人の長征が始まった。だが、一族全員が一度に移動すると目立つ上、外部から攻撃を受けた際に全滅させられる恐れもある。そこで、およそひと月をかけ、数家族ずつ南九州を脱出することになった。最後のひと家族が家を捨てるまで、集落の全戸で通常の生活が続けられているように完璧な偽装工作が行われたため、国司配下の役人が集落を調べに来たときは、すでに集落はもぬけの殻だった。
「シガツ一族は神隠しに遭った」
こんな噂が南九州全域に広まったころ、一族はすでに九州から本州へと関門海峡を船で渡り、瀬戸内海沿いの道を東に進んでいた。それが今からおよそ千年の昔、時は平安時代の中期のことだ。
その年の春のころ、シガツ一族は現在の広島、呉を通り過ぎ、竹原に差しかかろうとしていた。一行の本体は松林の奥深くで休息をとり、二十人ほどが浜辺や岩場に散らばって、周囲の警戒にあたる。
見張り役の一人が、戦装束を着た一人のNINJYAが岩と岩の間の波打ち際に浮かんでいるのを見つけ、棟梁を呼びに来た。
「棟梁、あれをご覧ください」
NINJYAは左肩のあたりに刀傷を負い、右の太ももに矢が刺さったまま、仰向けになって浮かんでいた。
「まだ息があるようだ。引き上げてやれ」
数人が海に入ってNINJYAに声をかけたが、虫の息で、小さな呻き声を上げるばかりだった。大柄なNINJYAを苦労して岩場に担ぎ上げたとき、岩場の向こうから三艘の櫓漕ぎ舟が現れた。それぞれに古びた鎧を身に着けた男たちが五、六人ずつ乗っている。棟梁は咄嗟に、手振りでNINJYAを隠すよう指示した。
「お前たちは何者だ?」
先頭の船に乗っている男がぞんざいな口調で尋ねてきた。棟梁は何も答えず、じっと男の顔を見つめている。
「お前、耳が聞こえないのか?」
「人に名を尋ねるときは、まず自ら名乗るのが礼儀だろう」
男は目を丸くむいて驚き、次に激昂した。
「何だと、この俺様を誰だと思う。来島水軍のハギューダとは俺のことだ」
水軍と言えば聞こえはいいが、連中は瀬戸内海を往来する船から法外な通行料をせしめたり、時に略奪も行う海賊の仲間だ。
「ハギューダ? 知らぬが、まあよい。私はシガツ・コノハーンという。旅の途中だ」
男はますます頭に血が上り、舟の上で地団太を踏んだ。おかげで舟が転覆しそうになったため、男の傍に立つ若い部下が慌てて声をかける。
「ハギューダ様、今はこんな田舎者の相手をするより、マリシエイのNINJYAを追うのが先決です」
ハギューダと名乗った男は田舎者という蔑みの呼び方が気に入ったらしく、機嫌を直した。
「そうだな、しょせんは田舎者。この俺を知らぬのも無理はないわ。おい、シガツとやら、黒い戦装束を着たNINJYAを見なかったか? 生きているか死んでいるかは分らんが、このあたりに流れ着いているはずだ」
海賊の端くれだけあって、潮の流れには精通しているようだ。
「いや、見なかったな。そいつは何者だ?」
「そいつはな……」
先ほどと同じ男がハギューダを制止する。
「先を急ぎましょう。今ならまだ、さほど遠くへ流れてはおりますまい」
「おお、そうだな。田舎者相手にとんだ道草を食ったぞ」
最後まで無礼で愚かなハギューダに比べ、部下の方が余程有能そうだ。
「その者の傷はどうだ?」
棟梁は三艘とも岩場の陰に消えたのを確認すると、岩場の窪みの中でNINJYAを看護している薬師に声をかけた。
「はい、傷はそれほどひどくはありませんが、海に浸かっている間にかなりの血が流れ出たようです。とりあえず、傷口を縫って血を止め、様子を見るしかありませんな」
「そうか。まもなく日も暮れる。今夜はこのまま松林に陣を張って、野営するとしよう。その者の手当てをしてやってくれ」
「しかし、見知らぬ者のために、どうしてそこまで?」
「先ほどの荒くれ海賊に追われていたのだ。悪い奴ではあるまいて。これも何かの縁じゃ。はっはっはっ」
棟梁は直観によって、この傷ついたNINJYAに何とも言えない縁を感じていたのだ。
結局、一行はこのNINJYAの手当てのために、三日三晩、この松林に留まった。瀕死のNINJYAは雨露をしのぐ天蓋付きの幕内に寝かされ、薬師が朝昼晩とシガツ一族伝来の薬湯を飲ませ、傷口に薬草を練った軟膏を塗り込んでやった。
NINJYAは四日目の朝、意識を取り戻した。
「せ、拙者は一体……」
「気がつかれましたか。私は薬師のタケダと申す。棟梁の命により、貴殿を看病つかまつった」
「棟梁とは?」
そこにコノハーンがやってきた。NINAJが起き上がろうとするのを制して言う。
「わしはシガツ一族の棟梁、コノハーンと申す。そなたが気を失って海に浮かんでいるのを見つけ、薬師に看病させた」
「かたじけない。拙者はマリシエイ派のNINJYA、マハンジャと申す」
「海賊がそなたを捜していたが、あまりに無礼な態度だったので追い払ってやった」
「それは、重ね重ね、かたじけない」
「なぜ海賊に追われておられたのだ?」
「その前に、拙者はどのくらい眠っていたのだ?」
「三日と三晩だ」
「な、何と! 姫は? 琴姫様の身が心配じゃ」
NINJYAは跳ね起きたが、身体を走った激痛に耐えかね、また倒れ込んでしまった。薬師が傷の状態を説明する。
「左肩の刀傷は長さ三寸、深さ一寸で、縫い合わせた。肺や心の臓は傷ついていないので、無理に動かさねば、ほどなく快癒しよう。右脚に刺さった矢は骨には達しておらず、毒消しの薬草を揉み込んでおいた」
「手厚く手当てしていただき、何とお礼を言えばいいのか」
コノハーンがマハンジャに静かに尋ねる。
「先ほど、琴姫様……と言われたが、事の次第をお話しくださらんか? 我らにできることがあれば、助太刀いたす」
マハンジャも、ここでジタバタしでも仕方ないと、腹をくくったようだ。
「我らマリシエイ派は、九州は筑紫を治める原田家に仕えるNINJYAでござる。原田家の二番目の姫がこたび京の五摂家の筆頭、近衛氏の親戚筋に輿入れすることなり、海路にて京までお送りする途中でした。周防の国の屋代島に停泊していると、海賊が夜陰に乗じて不意打ちをかけてきたのでござる」
無念やるかたない表情で、呻くように話し続ける。
「船室で眠っていた姫を何とか甲板に連れ出し、姫を抱きかかえて海に飛び込もうとした瞬間、脚を矢で射抜かれ、刀で切り付けられたのです。姫をお守りするのに精いっぱいで、不覚にも私だけが海に落ちてしまった」
「それで、姫はどうなされた?」
「水軍の中の一番立派な船に移されたのは、波間に浮き沈みしながら見届けました。しかし、その後は、お恥ずかしい話だが、気を失ってしまい……」
「さようか。恐らく、姫は身代金のかたに誘拐されたのであろう。だとすれば、助け出せるかもしれん」
「このような情けない有様でなければ、私一人でも取り戻せるものを」
「マハンジャ殿、ここは一つ、我らにお任せくださらんか?」
「任せるとは?」
「琴姫様をお助け申す」
マハンジャが驚いて、オウム返しに尋ねる。
「姫を、お助けくださると?」
「さよう。実は貴殿を海の中からお助けした時の経緯から、連中は我らに目を付けております。そこで、我らも狩りや山菜摘みをしながら、奴らの動きを探っておりました」
「ほう」
マハンジャの目に輝きが宿った。シガツ一族がただの流浪の民ではないと気づいたようだ。
「ここから一里ほど西に行った入江に、やつらの砦がある。来島水軍の本城は伊予の国にあると聞くので、そこは出城のようなものだろう。そこに、ひと際大きな船が泊まっておる。姫はその船の中ではないかな?」
「どのような船でござろうか?」
「ホクシャラク、絵図をこれへ」
コノハーンが幕の外に声をかけると、村人姿の男が入ってきて、懐から一枚の絵図を取り出した。コノハーンは絵図をマハンジャの前に広げて見せる。船の特徴を精巧に写し取った絵図だ。
「これだ! 姫が乗せられたのは、この船に違いござらん。それにしても、薬師殿の手当てといい、この絵図といい、見事と言うほかない。ご一族の皆さんの力量は測り知れぬようじゃ」
シガツ一族をただの田舎者と決めつけた先日の海賊と違い、マハンジャは人を見る目を持っている。
「それで、姫の年恰好はどのようで?」
「年は十六、背丈は五尺ほど、中肉の体つきでござる」
「ならば、わが娘のヨウンにそっくりじゃ」
「娘御がどうしたと申される?」
マハンジャが怪訝な顔で問う。
「この森の奥に、うまい野いちごが自生しておる。娘たち三人にそれを摘んで、船に売りに行かせます。そこで、我が娘が姫とすり替わって、船に残る。姫はほかの二人とともに船を抜け出します」
「しかし、それではヨウン殿の身が危ない」
「心配には及びません。あの程度の海賊どもが相手なら、ヨウンが一人で抜け出すのは赤子の手をひねるようなものです」
「そうは言われても……」
マハンジャがなおもためらっていると、コノハーンがもう一度、幕の外に声をかけた。
「ヨウンをこれに」
まだあどけなさの残る娘が入ってきた。
「改めて紹介いたそう。絵師ホクシャラクと、我が娘ヨウンでございます」
確かにヨウンの年恰好は姫とよく似ているが、顔つきはだいぶ異なる。姫が面長の瓜実顔なのに対して、ヨウンは彫りの深い顔立ちだ。
絵師が、筆先に異なる色の顔料を含ませた数本の絵筆を構えて声をかける。
「姫様のお顔の特徴を教えてくだされ。まずお顔の形はいかがかな?」
マハンジャが姫の顔の輪郭、目、鼻、口と、姫の顔の特徴を伝えると、それに合わせてヨウンの顔に絵筆を走らせる。何本もの絵筆を目にもとまらぬ素早さで操る姿は、まるで千手観音のようだ。
「いかがですかな?」
絵師が筆を置き、ヨウンの顔をマハンジャの方に向けさせる。
「これは驚いた。姫に瓜二つだ」
「姫が抜け出す際は、失礼ながら姫のお顔に墨を塗らせてもらう」
マハンジャもようやく、これなら無事に姫を救い出すことができそうだという気がしてきた。
そして、実際にその夜遅く、顔に薄墨を塗り、粗末な単衣を着た姫が連れ戻されてきた。姫は怪我をしてはいないようだが、憔悴が激しく、陣中の一番奥の幕内に敷いた布団に寝かされた。
その姫に、マハンジャが幕の外から声をかける。
「姫、お守りできずに申し訳ありませんでした。」
「そんなことより、私の身代わりになられた方のことが気がかりじゃ」
マハンジャの隣りにいるコノハーンが声をかける。
「四日もの間、船倉に閉じ込められ、助け出されたばかりだというのに、我が娘のことをお気遣いいただき、かたじけのうござる」
「礼を申さねばならないのは私の方です。マハンジャ殿、この方々のことを教えてくだされ」
マハンジャは自らが深手を負って海に浮かんでいたところを助けられ、ここに至るまでの経緯を簡潔に伝える。
「誠に、何とお礼を言えばいいのか分かりませぬ」
姫が言葉を続けようとしたとき、琴姫の着物を着たヨウンが何事もなかったような顔をして戻ってきた。コノハーンが娘に声をかける。
「おお、ヨウン、奴らはいかがしておる?」
「はい、私を姫様と信じ切って、船倉に閉じ込めたつもりでおります。今頃は野いちごに仕組んだ眠り薬が効いて、皆、ぐっすりと眠っておることでしょう」
「ならば、朝まで二、三刻(とき)は時間を稼げるな。では、琴姫様、マハンジャ殿、これより出立の仕度をいたす。もしかしたら、海賊どもからお国元に、身代金を要求する文が届いているやもしれません。我らが仕度をする間、姫様はお国元への文をしたためられるがよかろう。姫様の筆で無事を伝えれば、原田様もご安心なさろう。我ら一族の中で一番の走り手に持たせましょう」
「何から何まで、細やかなお心遣い、痛み入ります。ヨウンさんも本当にありがとうございました」
それまで黙って話を聞いていたヨウンが、姫に頭を下げて言う。
「姫様、申し訳ございません。色鮮やかな打掛は、姫様が寝ておられると思わせるために、夜具の上に広げて置いてまいりました。お許しください」
「どうか、頭を上げてください。そなたが無事に帰って来られたのですから、打掛など惜しくはありません」
半刻後には出立の準備が整い、疲れている姫と傷を負っているマハンジャは牛に引かせた荷車に乗せられた。数百人からなるシガツ一族は、物音一つ立てず、漆黒の闇に包まれた松林を抜けて行った。
夜が明けて、海賊どもはようやく姫に逃げられたことに気づいた。連中は慌ててシガツ一族が野営していた松林にやって来たが、時すでに遅し。姫の姿はもちろん、数百人がそこで数日間を過ごした痕跡すら残されていなかった。
シガツ一族と原田氏の姫たちはその日の夕刻、尾道の先の小さな入り江を見下ろす小高い丘に達した。そこで、入江の奥に大型の和船を見つけた。艫に〇の中に横三本の線を引いた家紋を染め抜いた軍旗を掲げている。
「マハンジャ殿、あれは、原田氏の家紋、三つ引両ではござらぬか?」
コノハーンが声をかける。
「確かに、あれはわが殿の家紋でござる」
艫に鎧を着た武将が立ち、配下の者たちは槍を手にして船の周りを警備している。
「あれに立っておるのが、姫を送り届ける一行の大将、木下阿須麻呂殿でござる」
船は奪われずに済んだのだ。
「さようか。ならば、お二人を船までお送りしよう」
コノハーンとヨウンが砂浜に牛車を引き入れ、船に近づいて行く。牛車に乗った姫とマハンジャを真っ先に認めた木下が本船に舫ってある小舟に飛び移り、浜に向かってやって来る。その顔は妙にこわばり、戸惑いの表情が混じり込んでいる。
木下は小舟が浜に乗り上げる前に海に飛び込み、腰まで海水に浸かりながら牛車に近づいて来る。波打ち際に達すると、牛車から降り立った琴姫の足元に土下座する。
「姫様、ご無事でしたか?」
木下はそう言って、額を砂にこすりつける。
「木下、もうよい。面を上げよ」
琴姫が木下に近づいたその時、木下は右手で鎧の下から小太刀を抜き、立ち上がった。小太刀の切先が琴姫の喉元に達する寸前、コノハーンが投げた鉄扇が、木下の右手首から先を小太刀もろとも跳ね飛ばした。
木下の右腕から血飛沫が噴き上がる。
琴姫もマハンジャも木下を味方として疑わずにいたため、虚を突かれ、咄嗟に反応ができなかった。だが、コノハーンは最初から、木下に違和感を覚えていた。
第一に、主君の姫君が海賊にさらわれ、四日間も行方が分からなかったにもかかわらず、木下には憔悴した様子が窺えなかった。姫を取り戻すべく海賊船を探すでもなく、入り江にただ停泊していたのも納得がいかなかった。そして、琴姫にわざとらしく駆け寄り、琴姫の足元にひれ伏したとき、右手を小太刀の柄に持っていくのが見えた。
コノハーンは木下の挙動を完全に見抜いていたのだ。
「き、貴様、何者だ?」
木下が手首から先がなくなった右手を抱きかかえ、鉄扇を投げた男を睨みつける。
コノハーンが名乗ろうとするのを制し、マハンジャが木下の胸に大刀を突き刺した。大きく開いた木下の口からは、叫び声の代わりに血反吐が噴き上がった。
「このような悪党にコノハーン殿が名乗ることはない。海賊どもの襲撃は、この木下が手引きしたに違いない」
海賊に誘拐されても気丈にふるまっていた琴姫だが、信じていた家臣の木下に裏切られ、すんでのところで刺し殺されそうになったことは、さすがに衝撃を受けたようだ。顔は青ざめ、身体がブルブルと震えている。
ヨウンがその身体を抱きしめ、優しく声をかける。
「もう大丈夫です。悪党どもは皆、ほら、ご覧の通りですよ」
船を見ると、木下の息がかかった者たちが、我先に海に飛び込んで逃げ出していた。
兵の半分は海賊に襲われたときに殺され、残りの兵の三分の二は逃げて行った。残った兵はわずか数人だが、幸いにも船頭と船員たちは全員が無事だった。
「さあ、このまま船に乗って京に向かわれるがよかろう。ちょうどよい西風が吹いておるので、海賊どもも追いつくことはできまい」
コノハーンが琴姫とマハンジャに出立を促す。
「コノハーン殿、ヨウン殿、本当にありがとうございました。このご恩は生涯忘れせん」
琴姫がそう礼を言うと、マハンジャが続ける。
「コノハーン殿には、何から何まで世話になりもうした。かたじけない」
「いや、礼には及ばぬ。当然のことを致したまでだ」
「万が一、琴姫様の身に何かあれば、我らマリシエイ一派は全員、死して殿にお詫びしなければならぬところだったのだ。このご恩を子々孫々まで忘れないために、この後千年、二千年たとうとも、我らマリシエイ一派はこのことを語り継ぐであろう。そして、我らマリシエイの血筋が続く限り、シガツ一族に生まれた姫に危機が及んだ際は、我らが最強のNINJYAが命を賭してお守りするであろう。このマハンジャが、コノハーン殿にお約束する」
琴姫一行と別れたシガツ一族は、この後十年近くにわたって、中国地方や四国地方の山中や海辺に住み着いては移動することを繰り返した。なかなか安住の地を得ることができなかったのだ。
一族が西国を諦め、京を抜けて北陸地方に向かう途中、琴姫と再会した。
琴姫はシガツ一族のおかげで、無事に五摂家の筆頭、近衛氏の親戚筋にあたる兼正伊織に輿入れすることができた。そして、今や朝廷の要職を占めるまでに出世した兼正との間に三男二女を設け、幸せに暮らしているという。
「コノハーン様、ヨウン様、あのときのお礼をさせてください」
流浪の身のシガツ一族を案じた琴姫は夫に掛け合い、その夫の計らいで朝廷から比叡山の西麓に住むことを許されたのだった。当時は猪や猿、ときには熊も出る山奥に過ぎなかったが、一族はその後四百年近くにわたり山林を開墾して農地を開き、狩猟をし、倹しく、しかし平和に暮らした。世間との関りは、雪に覆われて外に出ることができない冬場の手仕事として、家々で作った木彫り細工を売りに京に出るときぐらいだった。
足利将軍家が京の室町に幕府を開いた後も変わらぬ暮らしを続けていた。しかし、後に銀閣寺と呼ばれる慈照寺を建立した八代将軍義政の後継者争いから応仁の乱が勃発。その殺気だった京の空気が比叡山の麓にも及ぶと、これを嫌気した当時の棟梁が一族を引き連れて、東の国の奥多摩に移り住んだ。すると、かつてのシガツ一族の里は荒れ果て、また木々が生い茂るばかりの山林に戻っていった。現在の叡山ケーブルが走っているあたりだ。
以上が、シウンが父親のペンハーンから聞かされたシガツ一族とマリシエイ一派の『血の契り』の経緯だ。たった今、ガモンの攻撃からシウンを守ってくれたミカヅキこそ、その約束を果たしにやってきたマリシエイ一派の最強のNINJYAに違いなかった。
三人の伴を失い、傷心と心細さを胸に抱えるシウンにとって、今やミカヅキの存在だけが希望の光だった。シウンはその姿を思い出しながら、生まれて初めて、胸を締め付けられるような思いを感じていた。