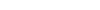✶ 第四幕 歓待の宴
ガモンの〝稲妻落とし〟に撃たれたジタンら三人は、辛うじて一命は取り留めたものの、とてもシウンの護衛として旅を続けられる状態ではなかった。シウンは三人に「迎えの者が来るのをここで待ちなさい」と言い残し、たった一人で海岸沿いの道を歩み始めた。
奥多摩を出た後、大菩薩峠から甲府盆地を抜け、河川沿いに太平洋まで下ってくるまで抱き続けていた高揚感は、もはや欠片もないまでに吹き飛んでしまった。シウンの心と身体は無力感と孤独、それに地面に沈み込むような激しい疲労に支配されている。
今にも倒れ込んでしまいそうなシウンの歩みを支えているのは、名望あるシガツ一族の姫としての矜持と、コノへワナキ・アイランドでアラキリヒルトによる洗礼を受け、世の中に平和をもたらすという使命感だけだった。今ここでシウンがくじけてしまえば、私利私欲にまみれた権力抗争は際限なく続き、罪なき人々の命も失われ続ける。
シウンが海沿いの道や時には砂浜を歩くのは、ガモンのほかにもシウンの行く手を阻む者がいるかもしれないからだ。そこかしこに監視カメラが林立する都市の中では、その者たちに発見されやすくなる。ミカヅキのおかげで九死に一生を得ることができたが、ガモンが放った4人の追っ手は、相変わらず一定の距離を置いて後をつけてくる。この上さらに、ほかの〝知事大名〟たちにまで居どころを知られ、刺客を送り込まれる事態は絶対に避けなければならない。
地球温暖化が加速度的に進み、日本列島は今や亜熱帯気候エリアに区分される。いわゆる梅雨はなくなり、初夏の乾季が終わると気温が急上昇し、いきなり夏の雨季を迎える。まだ六月に入ったばかりだというのに、まるでシウンの旅立ちに合わせたかのように昨日から気温が上昇し、浜辺では気の早い海水浴客たちが思い思いに海辺のレジャーを楽しんでいる。
シズオカシティーを抜け、大井川を渡って歩き続け、御前崎灯台に到達したところで、空がにわかに曇り始めた。小雨が降ってきたかと思ったら、すぐに土砂降りの雨になった。日本列島に今年初めて降る亜熱帯のスコールだ。
観光客たちは我先に、灯台の建物に駆け込んで行く。だが、シウンは傘も差さず、雨具を羽織ろうともせず、ただ大粒の雨に打たれるまま黙々と歩いている。
今のシウンの気持ちには、ずぶ濡れのみじめな姿がしっくりと合っていた。身体を雨に打たせることで、心は逆に癒されているのだ。
それに、シウンにはどうしても今日中にたどり着きたい場所があった。それは渥美半島の突端、伊良湖岬にある小さな集落だ。
シガツ一族が室町時代の応仁の乱に嫌気して京を離れ、関東に向かって移動している途中のことだった。
一族は気の荒い領主たちが群雄割拠する近江、美濃、尾張を避け、紀伊山地を抜けて伊勢に出ると、鳥羽から海路で伊良湖岬に渡った。
太平洋と伊勢湾や三河湾を分ける全長約五十キロの渥美半島の突端にある伊良湖岬は、今でこそ白亜の灯台が建ち、一帯は三河湾国定公園に指定される風光明媚な観光地だが、当時は太平洋の荒波がゴツゴツした岩に打ちつけ、低木が生い茂るだけの荒れ地だった。
だが、渥美半島の北側には波静かな三河湾と遠浅の干潟が広がっていた。シガツ一族一行は伊良湖岬にほど近く、三河湾に注ぐ川の河口で数日間、休息をとることにした。
干潟ではアサリやハマグリなどの貝類が豊富に取れ、滋養たっぷりの海藻が自生する岩場から様々な魚種の釣りをすることもできた。
ここを安住の地としてはどうかと言い出す者もいたが、棟梁は首を縦に振らなかった。棟梁が嫌ったのは、身を隠す高い山や深い森がない上に、三方を海に囲まれているため、半島の付け根の方から攻め込まれたときに逃げ場がないことだった。
「そういうわけで、我ら一族がここに根を生やすことはない。明後日にも出立する」
およそ百人いる家長の多くは棟梁の説明に納得したが、中には食い下がる者もいた。
「ここに残りたい者は残らせてはどうか?」
声を上げたのは棟梁の弟で、棟梁家を出て興した分家の家長だった。棟梁家の全員が息絶えたときには、新たな棟梁家となる血筋だ。賛同する者が二、三人いた。
全員が注目する中、棟梁はしばらく沈思黙考する。棟梁の頭に過ったのは、今で言うリスクヘッジだ。このまま一族全員で安住の地を求めて流浪することには、別の部族に襲われた場合に全滅させられる恐れが付きまとう。その点、本隊とは別に、いくつかの異なる場所に分散して集落を構えれば、たとえ一つの集落が滅んでも、他の場所でシガツ一族の血は存続できる。
棟梁は閉じていた目を開くと、キッパリとした口調でこう言った。
「よかろう、ここに残りたい者は残るがよい。ただし、ここで分かれても、我らは同じ血が通う一族だ。もしも一方に大事あれば、全員が馳せ参じてお互いを守り合うのだ。皆の者、よいな!」
棟梁がそう宣言すると、一族郎党こぞって拳を突き上げ、鬨の声を上げた。
こうして棟梁の弟の一家のほかに、何人かの家長とその家族が伊良湖岬の近くの地にコライミサキと名付けた集落を作り、自らをミサキーネと称した。以来ずっと、現代にワープしてきた今も、シガツ一族の棟梁家の分家筆頭として彼の地に暮らし、その長は代々、分け棟梁と呼ばれた。
スコールは一時間ほどで上がり、陽が再び射し始めると、今度は猛烈な蒸し暑さがシウンを襲う。それでもシウンは疲れ果てた心と身体に鞭打つように、同じシガツ一族の血が流れる人々が住むエリア・コライミサキの集落を目指して歩みを進めている。
夕刻が近づき、シウンがようやく浜名湖に差しかかったとき、浜名湖と太平洋をつなぐ水路の向こう岸に、シウンとよく似た娘が立っていた。シウンより三、四歳は年下だろうか。
「もしかして、シウン様ですか?」
声も話し方もシウンにそっくりだ。
「はい、シウンは私です。あなたは?」
「私はコライミサキに住むミサキーネの分け棟梁の娘、シレンです。奥多摩の大棟梁から父に連絡があり、シウン様をお待ちしておりました」
シレンはシウン一行がガモンに襲われ、三人の従者が傷ついたこと、どこからともなく現れたNINJYAがシウンを助けたことを知っていた。
「シウン様は乗り物にお乗りになれないと聞き、私も徒歩で参りました。お疲れのところ申し訳ありません。あと少しでございます」
シレンはシウンのリュックサックを手に持つと、シウンを促して並んで歩き始めた。
「ありがとう。助かります」
シウンの歩みは、速度が落ちたとはいえ、常人がジョギングするほどの速さはある。シレンも呼吸を乱すことなく、その速度に合わせて歩く。シガツ一族の一員として鍛錬は積んでいるようだ。
「シウンさんによい知らせもあります。ジタンさん、フゥさん、ダィクさんの三人は、先ほど奥多摩に到着されたそうです。薬師の見立てでは、三人とも命に別状はなく、数日間休養すれば病床を離れることができるだろうと」
その言葉を聞いて、シウンは幾分か救われた気がした。
シウンとシレンは国道四十二号線沿いに砂浜を歩いていく。渥美半島の最高峰である大山を過ぎると、辺りの風景は途端に寂れたものに変わった。それがシウンの心を幾分か落ち着かせた。
「あれをご覧ください」
うつむいて歩いていたシウンが頭を上げ、シレンが指さす方向を見ると、伊良湖岬の彼方に夕陽が沈んいくところだった。白亜の灯台がシルエットなって浮かび上がっている。あまりの美しさに、シウンは思わず息を呑む。
「きれい。胸が締めつけられるようだわ」
「私、生まれてからずっと、この夕陽を見ていますが、夕焼けは毎日毎日違うので、見飽きることがありません」
「奥多摩の夕焼けもきれいだけど、ここの夕焼けも素晴らしいわ」
「よかった。シウンさんの笑顔、初めて見たわ」
出会ってから一時間も経っていないが、二人はいつのまにか姉妹のように打ち解け合っていた。それがシウンにとって、何よりの癒しとなった。
夕陽を受けて半面が濃い橙色に染まる灯台の近くに、その集落はあった。都会では、金属より軽くて強靭な炭素繊維製のパネルや柱を組み合わせて建てた不愛想な一戸建て住宅が多いが、この集落は天然の木材や土などを使った住戸が多い。その中でひと際大きく、威風堂々たる趣のログハウスが分け棟梁の家、つまりソウンの家族が住む家だった。
シウンとソウンが集落に入ると、家々から人々が出てきて、二人の後に従う。石垣を組んだ台地の上にある分け棟梁の家に着くころには、その数は百人近くに膨れ上がっていた。皆、シガツ一族本家のシウン姫、過酷な使命を担って旅を始めた姫を一目見ようと集まったのだ。
石段を数段登った玄関先で、シガツ一族の分け棟梁ロンハーンがシウンを出迎えた。
「シウン姫、よくぞおいでくださった。ガモンとかいうNINJYAに襲われたと聞き、心配しておりましたぞ」
「ご心配いただき、ありがとうございます。シレンさんに迎えに来ていただいて、本当に助かりました」
シレンはこの場を早々に切り上げて、一刻も早くシウンを休ませてやりたいと思った。
「お父様、堅苦しい挨拶はそのくらいにして、早くシウンさんを皆に紹介してください」
「おお、そうだったな」
ロンハーンはシウンの手を取って、石段の下の広場の方を向かせた。
「みんな、よく聞いてくれ。こちらが、我らがシガツ一族の姫、シウン様だ」
夕陽を受けたシウンの顔は淡い紅色に染まっている。人々は、あまりに儚げで可憐なシウンを見て、驚きを隠せなかった。シガツ一族の姫としての使命を果たすため、過酷な運命に立ち向かうシウンを、人々はもっと逞しい女性だと想像していたのだ。
「あんなに華奢な姫様が、たった一人でコノヘワナキまで行くのか?」
「可哀そうに」
人々のざわめきを制して、ロンハーンが言葉を続ける。
「シウン姫は昨夜、奥多摩を出立されたばかりだが、早くも大変な試練に遭われた。しばらくの間、ここコライミサキで休息を取られる。今夜はゆっくりと身体を休めていただき、明日の夜、ミサキーネとして歓待の宴を開く。よいなっ!」
コライミサキがある渥美半島は、北は三河湾、南は太平洋、西は伊勢湾に囲まれ、アサリやハマグリ、タイ、アジ、シラスなどの魚介類が豊富に獲れ、温暖な気候を生かした野菜や花卉の栽培が盛んだ。自らをミサキーネと呼ぶシガツ一族の大半は漁業または農業で生計を立てている。
翌朝、ゆっくりと目覚めたシウンは朝食の後、シレンの案内で太平洋の荒波が押し寄せる恋路ヶ浜や、半島の突端に立つ伊良湖岬灯台などを見て回った。ミサキーネの人々は皆、笑顔でシウンを温かく受け入れてくれた。明るい陽光の下での暮らしは、悩み事や争い事など無縁のように思われた。
「皆さんは本当に、平和でよいところにお住まいね。うらやましいわ」
シウンがそう感想を述べると、ソウンは顔を曇らせた。
「いいえ、私たちにも知事大名同士の争いの波が押し寄せているのです」
「どういうことなの?」
「チューブエリアの中心都市ナゴヤの覇権をめぐって、シズオカのヨシモト一族とギフのドウサン一族が対立しているのはご存じですか?」
「ええ、それは知っているわ」
「その双方が、行政能力に長け、勤勉な私たちミサキーネを味方に付けようと、いろいろと画策しているのです。それで、父ロンハーンの命令で、家長の何人かはヨシモトの牙城であるケンチョウで働き、別の何人かはドウサンの拠点であるシヤクショで働いているのです」
「まあ、それじゃ、まるで人質だわ」
「でも、それは父の戦略でもあるのです。家長たちはそれぞれの組織の中枢近くにまで入り込んでいるので、私たちの一族は双方の機密情報に触れることがでます。それで、どちらかが圧倒的優位に立つことがないよう、密かに情報操作してバランスを取っているのです。勢力が拮抗していれば、おいそれと戦を仕掛けるわけにもいきませんからね」
「そうでしたか。のどかな暮らしに見えても、権力闘争の影は伸びてきているのですね」
まだ午前中だというのに、気温はぐんぐんと上昇してきた。二人はスコールが来る前にロンハーンの家に戻ることにした。
昼食をすませると、シウンは数人の男女に引き合わされた。年齢は三十代から四十代だ。リビングルームの中央にある円卓に、ロンハーン、シウン、シレンと彼らが着席する。
「シウン姫、ここにいる者たちはキョウトから中国、九州までを渡り歩き、各地の知事大名やNINJYAたちの動きを探っております。これから旅をされる場所について、何なりとお尋ねください」
「お心遣い、ありがとうございます。皆さん、シウンです。よろしくお願いします。では、早速ですが、ここを出てまず足を踏み入れるキョウトについてお聞きします。最近、ガシュー一族の傭兵NINJYAの姿をキョウトの中心部でしばしば見かけるようになったと聞いております。本当にそうなのでしょうか?」
シウンの正面に座っている化粧気のない瓜実顔の女性が口を開いた。
「はあ、そうどすなぁ。それらしい男たちを、錦町市場の辺りでよう見かけますわぁ」
ミサキーネの一員でありながら、完璧な京言葉だ。それだけ深く京都人に同化しているということだ。
「この間、小さな地震があったとき、あそこらへんの地盤が大きく歪んだそうどす。地下になにやらけったいな物があるらしゅうて、みんな、気色悪い言うてはりましたわ」
シウンの顔が急に曇ったことに、シレンは気づいた。
「シウンさん、どうかされましたか?」
「全国制覇を狙うガシュー一族が、西日本侵略の足掛かりとするため、キョウトに要塞を築いているという噂があるのです。要塞はきっとそこだわ」
「じゃあ、シウンさん、キョウトは避けて、伊勢から奈良を抜けて大阪に出るコースを行かれるといいわ」
「いいえ、シレンさん。この話を聞いて、ますますキョウトに行く必要が出てきましたわ」
「どうして、わざわざ火中に飛び込むようなことを?」
シウンは今からおよそ千年の昔、シガツ一族が朝廷の要職を務めていた兼正伊織の取り計らいにより、比叡山西麓に土地を得たことをシレンに話してやった。そのおかげで、一族はその後、数百年にわたる安息を得られたのだ。
「兼正家は現在も、キョウトで脈々とつながる朝廷に仕えておられます」
シレンにはにわかには信じられないようだった。
「でも、天皇家はトーキョーにおられますよ」
「あちらの天皇家は、陰陽で言えば、『陽』の方々。表舞台でご活躍です。キョウトの朝廷は『陰』であり、密かに知事大名たちの暴政や圧政を諫める役割を担っておられます。そして、朝廷直属の武将として、知事大名たちに睨みを利かせているのが、兼正家なのです」
シレンにも事情が呑み込めてきたらしい。
「ガシュー一族の西日本侵略の第一歩は、彼らにとって邪魔な兼正家を排除すること。そのために要塞をキョウトに作っているということですね」
「はい。ですから、大恩のある兼正家が危険に晒されていると知りながら、見て見ぬ振りはできません。また、兼正家は厳重に監視され、外部との通信はすべて傍受されています。こちらが要塞について知っているとガシュー一族に気づかれずにお知らせするには、私が兼正家のご当主に直接お会いするしかないのです」
「分かりました。シウンさん、私たちミサキーネもシガツ一族の一員として、キョウトに赴いてガシューの奴らと戦います。ねえ、そうするでしょ、お父様?」
それまで瞑目して話を聞いていたロンハーンが、重い口を開く。ロンハーンはむろん、シウンが話した朝廷や兼正家のことは熟知しており、シウンがキョウトに行かねばならぬ経緯も理解していた。
「シレン、それはならぬ。シウン姫は一人で行かねばならぬのだ」
「どうしてですか、お父様!? 各地に分かれて暮らすシガツ一族の分家は、お互いに助け合うのが一族の掟では?」
「その通りだ。だが、それは本家またはいずれかの分家が攻撃を受けたときのことだ。今回は本家もいずれの分家も攻撃されていない。今回一件は、あくまでシガツ一族本家の問題だ。我ら分家が手出しするわけにはいかないのだ」
「で、でも……」
食い下がろうとするソウンをシウンが制して言う。
「ロンハーン様のおっしゃる通りです。私は明日、一人で旅立ちます。だから、今宵は存分にご馳走になって、楽しませてもらうわ。シレンさん、よろしくお願いしますね」
シウンは「最後の晩餐に」という言葉を飲み込んだ。シレンにもそんなシウンの覚悟が伝わった。
太陽が伊勢湾に沈むと、ほとんど同時に、十七夜の月がコライミサキの東方にある標高三二〇メートルの大山の山頂付近から昇ってきた。昼間の暑さやスコールが嘘のように、涼しい風が穏やかに吹いている。
シウンとソウンは宴の前に、ロンハーンの家にある露天風呂で汗を流すことにした。湯船に十七夜の月が浮かんでいる。
思えば、シウン一行が十五夜の満月の光を浴びながら奥多摩を出立し、大菩薩峠にたどり着いたのが昨日未明のこと。その昼時にガモンの奇襲を受け、ジタンら三人が〝稲妻落とし〟に倒された。それからわずか一日半しか経っていないが、今日一日をソウンと一緒にのんびりと過ぎしたことで、それが遠い昔のことのように感じられる。それだけシウンは気力を取り戻すことができたということだ。
シウン歓迎の宴にはコライミサキで獲れた新鮮な海の幸山の幸がいくつもの大皿にふんだんに盛られ、数種類の自家製の酒も用意された。シガツ一族に伝わる独自の製法によって作られた日本酒やワインに似た醸造酒からウィスキーや焼酎などのようにアルコール度の強い蒸留酒まである。二十歳になったばかりのシウンもこれらの酒が振る舞われた。
ミサキーネの面々は男も女も、真剣をお手玉のように扱う剣の舞いや、アクロバティックな組体操など日ごろ鍛錬を重ねた技を披露する。農業や漁業で生計を立てる合間に、様々な武術の訓練をしているのだ。
宴もたけなわのころ、シレンがシウンに、何か見せてくれとねだった。
「これ、ソウン、姫に無理を言ってはいかん。今宵は、姫の心身を癒すための宴じゃ」
「そうでしたわ、お父様。シウンさん、ごめんなさいね」
浜昼顔の花を漬け込んだワインのような酒に頬を染めたシウンがニッコリと笑った。
「いいのよ、シレンさん。ロンハーン様、こんなに手厚くおもてなしいただいたお礼に、ほんの余興ですが……」
シウンは立ち上がると、両腕を胸の前で交差させ、両手の親指と中指を触れさせる印を結ぶ。目を閉じて、口の中で呪文を唱える。
すると、ざわついていた宴席が急に静かになったばかりか、草場で鳴いていた夏虫たちまで鳴き止み、上空を舞うように飛び交っていた蝙蝠の群れはどこかに消えた。生きとし生けるものが息をひそめ、動きを止める。聞こえるのは太平洋の荒波と三河湾のさざ波の音だけだ。一帯を静寂が支配し、はるか天空を流れる偏西風の音まで聞こえてきそうだ。
さらに術を続けようとしたとき、シウンはある気配に気づき、呪文を打ち切った。
シウンがコライミサキに入ってからはいなくなっていたガモンの手下の四人が戻ってきて、集落の外から監視していたのだ。四人は様々な騒音や人や動物の動きを隠れ蓑にして、巧みに気配を消していた。だが、シウンの呪文でその隠れ蓑がすっかり取り払われたために、四人の気配が浮かび上がったのだ。
ロンハーンもそれに気づき、そばにいた数人の若者に目配せする。彼らがスッと立ち上がると、ガモン配下の四人の気配は急速に遠ざかって行った。
人々の談笑や酒を酌み交わす宴のざわめきが戻り、夏虫や蝙蝠も活動を再開した。
「シウン姫、あの四人、今夜は近づいて来ることはありますまい。万が一、戻ってきたら返り討ちにしてやります」
「ありがとうございます。ロンハーン様にそう言っていただき、今夜も安心して休むことができますわ」
シウンはその後しばらくの間、シレンやロンハーンらとの会話と食事を楽しみ、早めに床に就いた。そして、朝まで一度も目を覚ますことなく眠った。
翌日は早朝から、強い東風が吹いていた。はるか南の太平洋上に台風が発生し、その中心から反時計回りに、強い風が渦を巻くように吹いているのだ。
朝食を終えたシウンにロンハーンが話しかける。
「シウン姫の旅には、人工の動力の付いた乗り物は使えないと聞いています。しかし、帆船なら乗ってもよいのだろうな?」
「はい、鹿児島からコノヘワナキへはヨットを利用するつもりでいます」
「ならば、ここから帆船に乗って伊勢に渡るがいい。我らの先祖がキョウトからこの地に下ってきたルートを逆に進むのです。ヨシモト一族とドウサン一族が角を突き合わせているナゴヤシティーは、避けて通るのが得策だろう」
シウンはソウンとともにミサキーネの漁師が操る小型帆船に乗り、伊勢湾の対岸の鳥羽に渡った。ここでソウンたちと別れたシウンは、伊勢湾沿いに北上し、布引山地に分け入る。その足取りはコライミサキにたどり着くまでと違って力強く、キビキビとしている。昼には伊賀盆地を抜け、水口丘陵に源流を持つ野洲川の上流に達した。
ここから野洲川沿いに下ってシガの琵琶湖に出れば、今日のうちにキョートの兼正家にたどり着けるはずだった。
だが、シウンの行く手は、またもやガモンとその手下たちに阻まれることになる。彼らは琵琶湖の畔に罠を仕掛け、シウンの到着を今や遅しと待ち構えていたのだ。