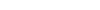✶ 第五幕 セツエンの襲来
シウン姫は布引山地から伊賀盆地を抜け、広く琵琶湖を見晴らす水口丘陵に出た。そこから琵琶湖に流入する野洲川沿いに下って行き、ついに琵琶湖に到達した。琵琶湖大橋を渡って比叡山地を超えて大原に出る。そこから高野川沿いに南下し、およそ700年前までシガツ一族が暮らしていた八瀬を抜け、キョート市内に入るルートを取るつもりだ。
「ここまで来たら、兼正家のある六波羅まで、あと少しだわ」
全長1400メートルの琵琶湖大橋を渡る途中、欄干に手を置き、さざ波が立つ湖面を眺めているときだった。湖面からキラキラと乱反射してくる光の中に、ひと際赤く輝く光の塊があった。シウンが無意識のうちに身体をかがめると、赤い光線が左肩をかすめた。その瞬間、シウンが手を置いていたのと反対側のコンクリート製の欄干が三メートルの幅に渡って木っ端みじんに吹き飛ばされた。
「ガモンか?」
「いかにも!」
「不意を襲うとは、相変わらず卑怯な」
「NINJYAの闘いに卑怯も何もない。勝てばいいのだ」
そのとき、シウンの頭上に淡い影が差した。咄嗟に身体を回転させながら欄干に飛び乗る。空中から舞い降りてきた赤いベールが投網のように広がり、シウンが立っていた場所を覆う。ベールを放ったのは空中に浮かんだ女だった。
「このセツエンの攻撃をかわすとは、大したものだ」
赤いベールはスルスルとセツエンの身体に巻き取られていく。ほんの数秒だったが、ベールに覆われていた地面は真っ黒に焼け焦げている。セツエンが次に放ったのはお水色のベールだ。シウンは道路の反対側の欄干に飛び移ってかわす。すると、直前までシウンが立っていた欄干が水浸しになって壊れていた。
自らセツエンと名乗った女は、女NINJYA『くノ一』に違いない。身にまとった様々な色のベールを武器として使っており、ベールの色によって火炎噴射、高圧水流といった攻撃に使い分けるらしい。幾重もの薄いベールに包まれたセツエンの見事なプロポーションが、逆光の中にシルエットとなって浮かび上がる。
身体に巻き付いたベールを放つと、その部分の雪のように白い肌が晒される。恐るべき破壊力を持つと同時に、妖艶さで敵の目を眩ませる効果もある。セツエンは上空に飛ばした自動操縦のドローンから下ろした透明のベーで身体を吊っているのだ。ドローンに搭載されたAIがセツエンの意図を察知し、飛行速度や高度を瞬時に調節する。
ガモンとセツエンのほかに、三人の敵が姿を現した。奥多摩を出たときから尾行していた四人のNINJYAとは格が違うらしい。セツエンらは今の今まで、シウンに一度も気配を察知させなかった。」
「俺はシラタ」
「私はミレ」
「俺はブコだ」
ガモンも含めて三人のNINJYA、二人のくノ一は皆、戦装束を着ている。本気でシウンを亡き者にしようというのだ。
セツエンのほかの三人は一体どんな術を使ってシウンを攻撃してくるのか。全く予想がつかない中、シラタと名乗ったNINJYAがジリッと、シウンとの間合いを詰めてきた。・・・・はシウンの右から背後に回り込もうとし、・・・・は左から回り込もうとする。相変わらず上空にはセツエンがいて、いつでもベールを放つ態勢を取っている。
まさにシウン包囲網が完成しようとしていたとき、セツエンを吊っているドローンが勝手に大きく移動し、セツエンは一瞬のうちにシウンの上空から百メートルも引き離される。皆がセツエンの行方に気を取られ、シウンから目を離した隙に、一人のNINJYAがシウンの前に庇うように立っていた。ガモンが声を発する。
「現れたな、ミカヅキ。そろそろ出てくるころだと思っていたぞ」
セツエンもすぐにシウンとミカヅキの上空に戻ってきた。
「おまえがミカヅキか!? よくもこのセツエンをコケにしてくれたな。ミカヅキは私が倒す。シラタ、・・・・、・・・・、手出しは無用だ」
そう言うが早いか、セツエンは先ほどシウンに見舞った火炎噴射のベールをミカヅキに放つ。ミカヅキは三日月形の武器・・・・・で、ベールを難なく切り落とす。続いてセツエンが放った高圧水流のベールも同じ結果になった。
「先ほどのシウンへの攻撃で、おまえの術は見切って……」
ミカヅキがそう言いかけたとき、セツエンは、今度は半透明のベールを投網のようにミカヅキとシウンの頭上に広げた。半透明のベールはいつまでも落ちて来ず、二人の頭上に留まり、えも言えぬいい香りの霧を振り撒いている。すると、ミカヅキの目に、セツエンの身体が純白に光り輝いて見えた。その霧はセツエンの得意技・白艶霧だ。
「まんまと掛かったな、ミカヅキ。最初の二つのベールはオトリだったのさ」
シウンの目にも、ミカヅキに異変が起きているのは明らかだった。セツエンの術は男にだけ威力を発揮するものらしい。ミカヅキはみるみる衰弱し、今にも琵琶湖大橋の上に倒れ込みそうだ。セツエンがミカヅキを無力化している間に、ガモンがシウンの肩を捉えようと手を伸ばした。
と、そのとき、ミカヅキは三日月型剣で自らの左腕を切り落とし、その傷口から大量の血しぶきを噴射させた。誰もがその行動に度肝を抜かれた。
「シウン姫、ご免!」
ミカヅキはその隙に、シウンの身体を数百メートル先の湖面まで吹き飛ばした。
並みの人間なら着水の衝撃で骨折したり、命を失いかねないところだが、シウンは着水する直前に身体を丸めて衝撃を和らげ、そのまま湖面を前転して進み、岸辺までたどり着いた。
シウンはそのまま、ミカヅキの方を振り返ることもせず、全速力で疾走し、姿を消した。薄情なわけではない。ここでミカヅキを助けに戻り、ガモンらに捉えられれば、捨て身の術を使って逃がしてくれたミカヅキの好意が無駄になってしまう。ミカヅキに報いるには、この場を生きて逃れるほかないのだ。
ミカヅキが腕を切り落とし、血しぶきをまき散らしたのは目くらましの術で、実際には腕を切り落としてなどいない。だが、シウンを逃れさせることはできたものの、持てる力のすべてを使い果たしたミカヅキは、琵琶湖大橋の上でガモンらに捕らえられてしまった。
「皆の者、ミカヅキを殺すんじゃないぞ」
「でも……」
「こいつの強さの秘密を知りたいのだ。キョートの要塞に連れて行き、徹底的に調べ上げるのだ」
セツエンは先ほどミカヅキとシウンの頭上に広げた純白のベールを自分の身体からはがすと、ミカヅキの身体に巻き付ける。ミカヅキは完全に動けなくなった。
琵琶湖大橋を見晴らせる春日山公園に隠れていたシウンは慎重に気配を消し、後をつける。ガモンらは短刀で藪を切り開きながら比叡山地をほぼ一直線に突き抜け、比叡山南麓の一条寺勢ヶ谷から音羽川沿いにキョートの市街地に下って行く。修学院離宮の南側を抜け、高野川、鴨川と川沿いに中心部に向かう。三条大橋を渡ってナカギョークに入り、古都の風情が残るニシキマーケットに到着した。
そして、ミカヅキをマーケットストリートの裏手にある一軒の変哲もない町家に運び込んだ。シウンは、その町家こそ、ミサキーネのキョート調査員が教えてくれた要塞の入り口に違いないと確信した。
シウンが睨んだ通り、ガモンらは町家の土間を抜けて裏庭に出ると、大きな土蔵の前に立つ。観音開きの扉の上に仕込まれたセンサーが、ガモンの身体のあらゆる特徴を検知し、すぐに重い扉が音もなく左右に開いた。この要塞のセキュリティーを統括するAIが、そこにいるのがガモン本人だと認識したのだ。
ガモンらがガランとした土蔵の中に入って床の中央に立つと、今度は床全体が音もなく沈み始め、地下深くまで下りていく。
床が停止すると、そこにはバスケットボールのコートほどの広さの部屋があった。中央に十脚ほどのハイバックチェアが並ぶ楕円形のテーブルがあり、部屋全体が様々な電子機器が整然と並ぶ壁に囲まれている。闘いの指揮を執るオペレーションルームだ。
ガモンが部屋に入って行くと、そこで作業していた数人の者たちが一斉に両足を肩幅に開き、胸の前で右手の拳を左手のひらで包む。ここでの最高権力者への最敬礼のポーズだ。
ガモンは彼らにぞんざいな挨拶を返すと、奥の扉の前に立つ。ここでもセンサーがガモンの身体の隅々までチェックすると、セキュリティーAIがガモン本人だと認識して扉を開けた。
驚いたことに、そこは体育館ほどの広さのあるドーム状の広大なスペースだった。今はまだガランとしているが、二日後には大量の武器や弾薬が運び込まれる予定だ。
その中央に手術台のようなテーブルが置かれ、ミカヅキはその上に放り出された。セツエンが身に着けていた純白のベールでグルグル巻きにされたままだ。
「ミカヅキ、覚悟はいいな。これからお前の身体を徹底的に調べさせてもらう」
ミカヅキは何も答えなかった。いや、セツエンのベールの魔力で、指一本、眉一つ動かすことができないのだ。セツエン得意の術、白艶布だ。セツエンが巻き付けたベールに気力、体力のすべてを吸い取られ、ミカヅキはまるで泥沼の底に沈んでいくような恐ろしい虚脱感に襲われていた。
ガモンたちが入ってきたのとは別の扉が開き、ガモンのアンドロイド手術をしたサージェントメカニック、通称〝手術屋〟が入ってきた。黒ずくめの手術着を着て、いくつかの機材を乗せたワゴンを押し、ミカヅキが横たわるテーブルに近づいて来る。
「手術屋、よく来てくれた」
「ガモン様、その後、お身体の具合はいかがですか?」
「そんなことより、早くこのミカヅキの身体を徹底的に調べてくれ。こいつの強さの秘密を知りたいのだ。場合によっては死なせても構わん」
手術屋が残忍そうな笑みを浮かべ、舌なめずりする。
「承知しました。こんなにおいしい仕事は久しぶりですよ」
手術屋はミカヅキの身体を切り刻むからりに、自ら考案した様々な機器を使って調べていく。強力な超音波や電磁波、放射線、レーザーなどをミカヅキの身体の隅々にまで当てていく。
その一つ一つがミカヅキに、メスで身体を切り刻まれる拷問に等しい苦痛を与えているのだ。先刻までピクリとも動けなかったミカヅキが、セツエンの白艶布に巻かれたまま、テーブルの上でのたうち回る。
その姿を満足げに眺めていたガモンだったが、途中から手術屋がしきりと首をかしげるようになったのを見て、声をかけた。
「手術屋、どうした? 何があったのか?」
「いえ、その逆で、何もないのです」
「ない? 何も?」
「はい。非常にバランスよく鍛えられた肉体であることは確かですが、それだけなのです。特別な装置や機器が埋め込まれているとか、どこかの器官が異常に発達しているといったことはありません」
「それは間違いないな?」
「はい。間違いございません」
ガモンは失望の色を隠せなかった。ミカヅキの身体に何か特別な物が見つかれば、それを取り出して自分の身体に移植しようと考えていたのだ。
手術屋が持ち出してきた機器では解き明かすことはできなかったが、むろん、ミカヅキの強さには理由がある。それは神経伝達物質の質と量が人並み外れて優れていることだ。身体能力の高さ、筋肉や骨の強靭さ、反射神経の鋭さ、頭脳の明晰さと瞬時の分析能力……これらすべてをつかさどっているのが、全身の細胞の間を駆け巡る神経伝達物質だ。
そして今、手術屋がミカヅキに浴びせた超音波、電磁波、放射線、レーザーがミカヅキの神経伝達物質に激しい刺激を与え、覚醒させた。セツエンの術にはまってほとんど活動を止めていたミカヅキの全身の細胞の一つ一つに、覚醒した神経伝達物質がエネルギーを注入し始めたのだ。
ミカヅキは全身に力がみなぎってくるのを感じていた。気合を集中し、身体に巻き付けられたベールを内側から引き裂こうとしたときだった。
ドアが開き、隣のオペレーションルームから人が飛び込んできた。
「何事だ? 騒々しいぞ」
ガモンが苛立たし気に言うと、その男は直立不動の姿勢をとった。
「は、はい。申し訳ありません」
「何があったんだ?」
「はい。何者かが裏庭に侵入し、土蔵の前に立っているのです」
「何だと! それを早く言わんか!」
ガモンはオペレーションルームに駆け込み、モニターを見る。そこには、なんとシウンと四人のNINJYAが映っていた。
ガモンは一瞬、我が目を疑い、次に大声を上げて笑い出した。
「飛んで火に入る夏の虫とは、このことだ」